
正答率は気にしたほうがいいの?
・正答率をどう使えばいいの?印刷されているけど使い方がわからない。
正答率について塾から言及がなかったことで「ふーん」と終わらせていたのが大失敗でした。
我が家の正答率利用法をご紹介します。
正答率より偏差値重視で失敗
塾のテストを受けると必ず「正答率」の表示があります。



正答率は気にしたほうがいいの?
正答率の疑問を持ちながらも、すぐに忘れてしまい子どもの塾生活は過ぎていきます。
塾でいわれることと言えば「解き直しをする問題は全て」といわれ、正答率についての言及はありません。
塾で正答率について重要視していたら、言及してもよいはずだと思うのですが一言もありませんでした。
塾のクラス分けは(たぶん)偏差値なので、私はテストの結果は点数と偏差値しか見ていませんでした。



正答率が高い問題なのに解けてないね、次は頑張れ!
正答率をみて感じることと言えばこの程度です。
正答率が低い問題は誰のため?
塾の先生とお話をしていた時に、テスト問題の内容などについて話をすることがありました。
内容を簡単にすると
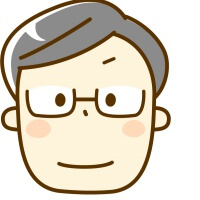
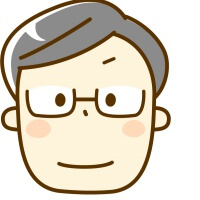

正答率が低い=難しい問題ということ。
難しい問題を出さないといけない理由はトップクラスにいる子たちのため。難しい問題を出さないと点数に差が出ない、試験中に暇になるという理由もある。
先生の言葉は腑に落ちました。
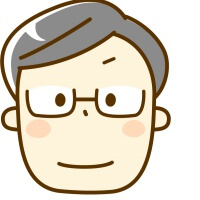
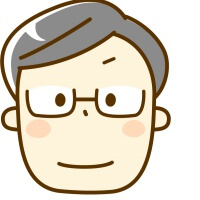

正答率1桁のものはトップクラス用ですから気にしなくていいです
うちの場合、解けなくても気にしないでよい問題だったということです。
モヤモヤしている時間がもったいなかった。
それなら正答率から何か対策ができるのではないか?と考えました。
正答率50%以下の問題は解き直しをしないという決断



正答率がどれぐらいまでの問題は解けないといけないの?
直近のテストの結果を使って、正答率が90%~10%台までのものをそれぞれ全部正解した場合の点数を各教科ごとそれぞれ計算しました。
正答率が100%~50%台のものが確実に取れるだけでも、かなり点数が取れることが分かりました。
計算で出てきた点数から、我が家の目安は正答率が50%台の物までは確実に正解することを目標にすることにしました。
気になる人は、直近のテストで確認してみてください。驚く点数が出てきますよ。
子どもに説明、そして行動



正答率が50%のものが取れると〇点だよ。



半分の人が答えられる問題は、できるほうがいいね
正答率50%なら〇点、正答率40%のものなら〇点と、正答率毎に取れる点数を明確に伝えることで解きなおす問題を絞ることができました。
与えられた問題をすべて解けるようになればいいですが「基本をしっかりと抑えられたらよし」という考え方にしました。
タブレットで解き直しを管理
正答率を見ることで、効率よく受験勉強ができたのではないか?と思うようになりました。
解き直しをするときに利用したのはタブレットです
「暗記マスター」というアプリを使用して管理しました。


- 問題・解答・正答率をアプリに入れる
- 正答率が〇%で間違えた問題のみを解けるようになるまで何度も解く
この方法を行ったところ、確実に解ける問題が増えていきました。
必ず解かなければならない問題の選別が正答率からできたことで、限られた時間を効率よく使うことができるようになりました。
正答率が50%までの問題がクリア!次は40%をめざして
50%までの問題が確実にできるようになれば、かなりの点数が期待できます。
目標とする正答率を決めたことで、気持ちが楽になりました
正答率の低いものが正解だったしても、たまたま正解したのなら意味を成しません。
正答率の高いものを確実に正解にすることを目標としたことで、テストの点数につながっていきました。
おまけ:過去問の正答率を公表しているのは本郷中学
本郷中学校では入試問題の過去問・解答例・正答率を公表しています。
入試問題の正答率を公表している学校はとても珍しいです。
本郷中学校を受験する人は正答率まで見れることで、必ず正解しなければならない問題や合否を分けた問題もわかるかもしれません。
過去問対策をしたときに、多くの人が解けた問題を落としていないかチェックできますね。




コメント