
理科が分からない、覚えられない
わが子がそんなふうに感じ始めたのは、小学5年生のころでした。
「実験ってやってるの?」「解剖とかしてるの?」と聞いたら「やってないよ」と返ってきて、少し驚きました。
それなら、手を動かして学べる場を探してみようと思い、理科実験教室を調べ始めました。
通ってみると、子どもの反応にも変化があり、わが家にとってはとても良い経験になりました。
この記事では、理科実験教室を選んだ理由や授業の様子を、体験をもとにまとめています。
先生たちが教えてくれた「体験の大切さ」


「手を動かして行ったことは、体が覚えています。どんどん体験させてください。体験した子は理解度が全く違う。経験することは本当に大事で、成功でも失敗でも、それがその子の糧になるんです」
そう話していたのは、中高一貫校の学校説明会で出会った校長先生でした。
保護者会で塾の先生も、こんなふうに話してくれました。
「普段の生活や会話の中に、体験できることを入れてみてください」
重さや距離の感覚は、実際にやってみないとわからないからこそ、家庭の中で体験できる工夫をしてみてほしいということでした。
- たとえば、こんな方法(例)
- ・1gはどれぐらい少ない量なのか、実際に測ってみる
・1kgと1000gは同じ?違う?実際に測ってみる
・車で出かけるようなことがあったら、ここまで何キロだよと会話に入れる
・ご飯をよそってみて「これはどれぐらい?」と当てっこする
・牛乳などを計量する
ご飯の支度を手伝わせるときや、外出先での会話の中でちょっとしたやりとりを通して、家庭でも理科につながる体験を積み重ねていくことができるのだと感じました。



どんなことでも「一度やったことがある」という経験は自信にもなりなすね
小学校と塾の授業で理科が苦手に
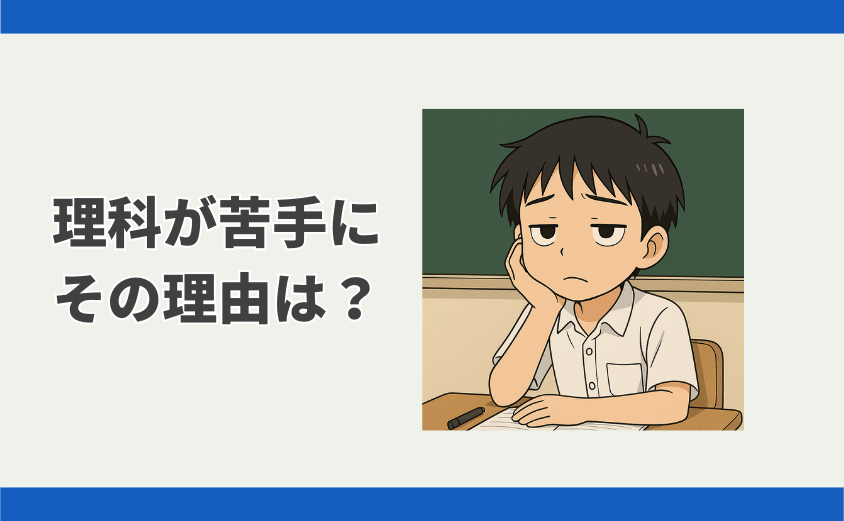

小学校や塾の授業の様子を見ていて、「これでは理科が苦手になるかもしれないな」と思ったことがあります。
子どもがただ話を聞いているだけになっていたり、実験の話がまったく出てこなかったりして、「このままで大丈夫かな」と不安になりました。
小学校の授業では実験が足りない
私の小学生時代を思い出すと、けっこう頻繁に実験をしていた記憶があるので、今も実験の数は大丈夫だと思っていました。
私が印象に残っているのは「フナの解剖」、主人は「カエルの解剖」だったそうです。
ところが、わが子から解剖の話をまったく聞いたことがなかったので、「今ってどうなってるの?」と聞いてみるとビックリ。



煮干しを爪楊枝を使って解剖するんだ。
やりにくいんだよ~!!
みんなぐちゃぐちゃになって失敗してた。
5年生の保護者会で、小学校の理科の実験について先生に聞いてみたところ、



学習指導要領が変わり、年々実験する機会が減っています。お母さん方の時代と比べると、実験数も内容も変わっています。
そのとき初めて、小学校での実験がかなり減っていることを知りました。
塾の授業で理科嫌いになった
小さいころから科学技術館や日本化学未来館などに連れて行っていたこともあり、理科は好きな科目でした。


ところが、塾の5年生の理科の授業に入ってから、だんだんと理科が嫌いになっていきました。
- 座学だけの授業なので退屈
- 図や文章だけで理解するのが難しい
- 授業の内容が毎回変わるので、覚えられない
黒板に絵をかいて、先生が淡々と説明するだけの授業で、子どもにとっては「ただ聞いているだけ」になっていました。
もし、映像を使って見せてくれたり、ちょっとした実験を取り入れたりしていたら、きっと印象も違っていたと思います。
でも現実はそうではなく、子どもにとって理科は「暗記科目」という位置づけになってしまい、机の上だけで進む授業ではうまく理解できず、点数も取れなくなっていきました。



あんなに好きだったのに…どうしたらいいんだろう…
実験教室を探し始めたときのこと
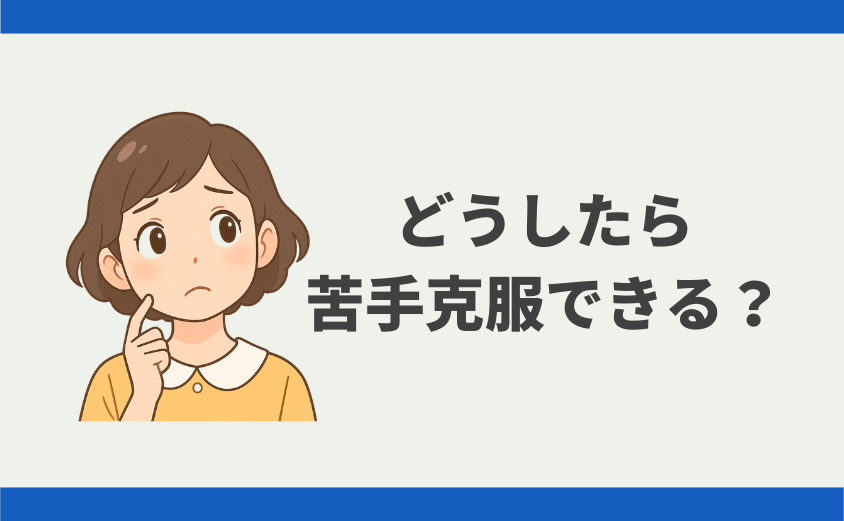

わが家は、一時的に大手の中学受験塾をやめていた時期がありました。
算数だけは専門の塾に通っていましたが、理科・国語・社会については自宅で勉強するしかありません。
そこで、なんとか理科の理解を深められないかと考えて、理科実験教室を探すことにしました。



自分で先生を選べると思ったら、調べることも前向きな気持ちになりました
理科実験教室に通ってわかったこと、感じたこと
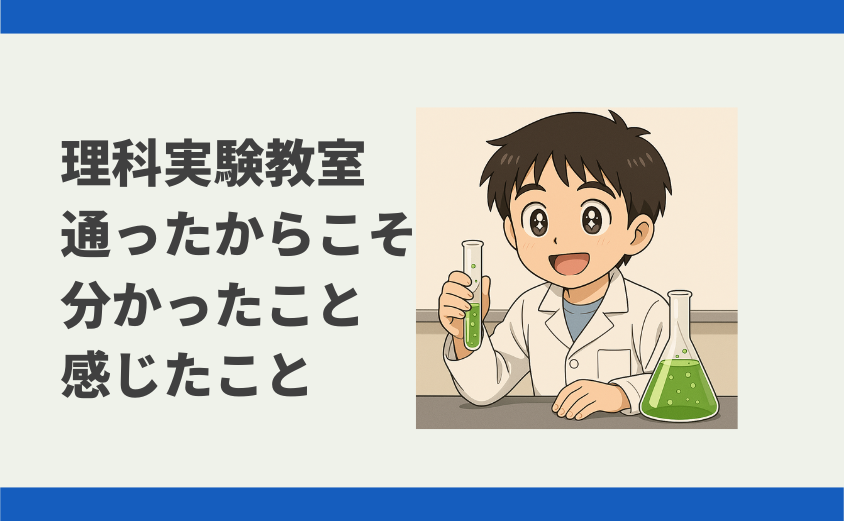

理科実験教室に通い始めてから、子どもが理科に対して前向きになっていく様子が見られるようになりました。
ここでは、体験授業の流れや授業中の様子、実際に通ってみて印象に残っている授業など、わが家が感じたことをまとめてみたいと思います。
体験授業の流れと子どもの反応
わが家の場合、体験授業は通常授業に参加させてもらうことで行いました。
2時間の授業の内容は、以下のようになっていました。
- 仮説を立てる
- 実験する
- 結果の検証
- 考えをまとめる
- 今回行った実験の小テストをする
2時間は長丁場だと思っていましたが、あっという間に終わりました。
実験教室の体験が終わったときに、子どもが興奮気味に話をしていました。



実験楽しい〜!またやりたい!
子ども自身が気に入ったこともあり、その場で理科実験教室に入塾しました。
6年生の夏休みで理科実験教室は6年生の授業が終了することもあり、通った期間は1年とちょっと。最後のカリキュラムまで通塾しました。
「触れない子」が挑戦した解剖授業
実はうちの子、大きい、小さいにかかわらず動物には一切触れませんでした。
理科実験教室3回目の授業はウシガエルの解剖。



今日の内容は解剖なんだけど、大丈夫かな?内容を言ったら行かないと言われそう
面倒なので言わないまま授業に参加することにしました。
授業が始まったときに「え?マジ??」という顔をしたわが子。
麻酔にかかった大人の手よりも大きいサイズのウシガエルを見て嬉しそうな生徒たち。
「げー、やだー。怖い!」なんてことは無く「やったー!待ってました!」ぐらいな勢い!
その雰囲気も良かったのかもしれません。2〜4人のグループでウシガエルを1匹を解剖します。
自分から手を出さないと、他の子がガンガン解剖してしまいます。
同じ年齢の子が楽しそうに「これなに?胃かぁなぁ。」なんて言いながら、あらゆる臓器を取り出して、触って感想をいいます。
勇気を振り絞って触ってみたら「あれ、大丈夫だ。触れる!」という顔に、その後は楽しそうに素手で解剖していました(※手袋はありますが使っている子はあまりいませんでした)。



体験するってすごい!
この時から、生き物に触るのが徐々に大丈夫になりました。
印象に残った実験や夏の合宿
私の印象に残った授業では、水溶液の授業があります。以下のような実験がありました。
【問題】中身がわからない水溶液が8種類あります。その水溶液は何ですか?試薬・器具などは自由に使えます。但し、飲むのは禁止。
用意されている試薬や器具を使ってグループで問題を解いていきます。
グループで知恵を出し合い話し合いをしながら答えを導き出します。
試薬を入れ出てきた結果をもとに考え、繰り返し試すことで頭に蓄積されました。
夏休みには合宿があり、朝から晩まで実験三昧の時間を過ごしたり、通常の授業では体験できない地学実習なども参加しました。



合宿などは自由参加です。普段できない1日を通した実験をすることができるので楽しくいい思い出になったようです
理科実験教室を選ぶときに意識したこと


理科実験教室には、大手塾が運営している教室もあれば、個人で運営している少人数制の教室もあります。
カリキュラムの一貫性や安心感で大手を選ぶか、子どもの反応や距離感を重視して個人教室を選ぶかは、ご家庭によってさまざまだと思います。
わが家は、場所や時間帯、教室の雰囲気など、子どもが無理なく通えることを一番に考えて、個人でやっている理科実験教室を選びました。
通塾頻度は月に1回~2回程度で、学年によって異なっていました。
最近は、オンライン対応やマンツーマン指導など、スタイルもいろいろあります。
- 四谷大塚:大手塾の中でも実験要素を取り入れた授業がある校舎も。受験対策と連動しやすいのが強み。
- 栄光サイエンスラボ:体験を通じて理科好きになることを重視。継続的に通えるカリキュラム構成。
- ユリウス関西(日能研グループ):個別指導で、子どもの理解度に合わせて楽しく進められる実験プログラム。
- しゅん吉クエスト



体験授業があれば参加してみるのもおすすめです
実験教室のメリットと注意点
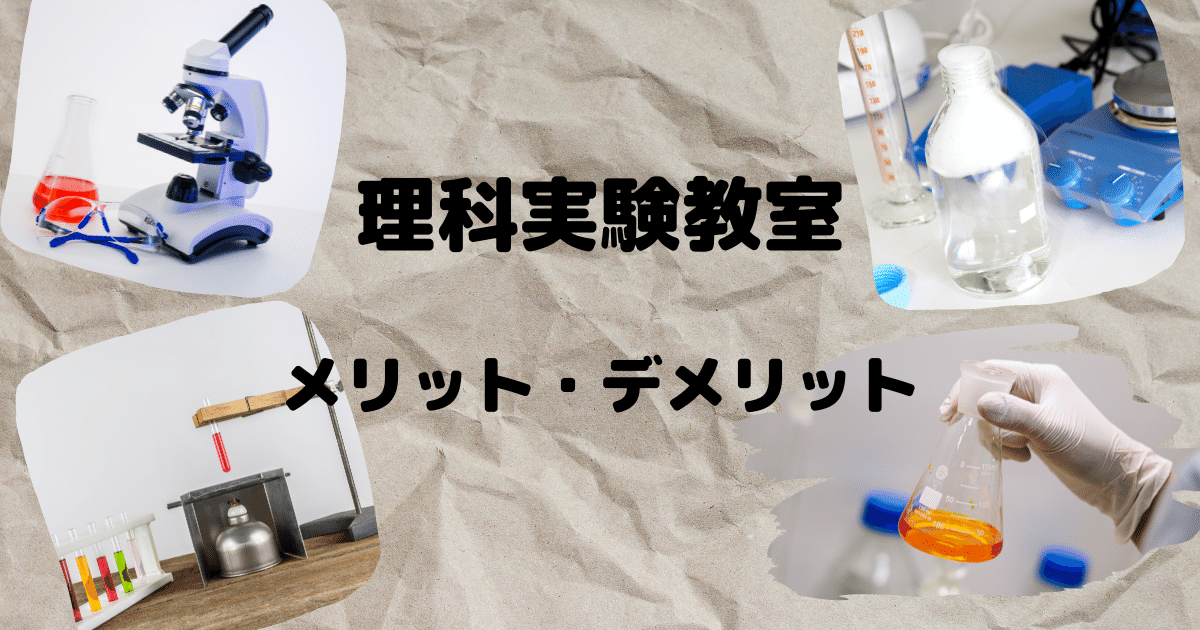

理科実験教室に通ってみて、わが家にとっては良い影響が多かったと感じていますが、もちろん気になる点がまったくなかったわけではありません。
ここでは、実際に通ってみて感じたメリットと注意点について、体験をもとにまとめてみたいと思います。
手を動かすことで記憶に残る
理科実験教室に通塾したことで、実験教室で行った実験問題は確実に取れるようになりました。
1回の授業でも手を動かして体験し、試行錯誤したものは忘れずに覚えていました。
たとえば以下のようなもの:
- 顕微鏡の使い方、ガスバーナーの使い方など、実験用具の取り扱い方
- 触ったときの感覚
- 実際の結果
- 感動や驚き



座学と違い、受け身の授業よりも体験する授業のほうが記憶に残ります。
道具や白衣がモチベーションに
理科実験教室では、顕微鏡やフラスコ、ガスバーナーなどの器具を実際に使うことができます。
ふだんの学校ではあまり触れない道具にふれることで、子どもの気分も高まります。
また、白衣を着て授業を受けるスタイルだったので、気持ちが切り替わり、「今日は特別なことをする」という意識も高まっていたように思います。
回数・費用の面での注意点も
理科実験教室のデメリットとして感じたのは、まず費用面です。
月に1回〜2回の頻度で通うスタイルが多いですが、1回の授業が2時間程度と長めで、講座の内容も専門的なので、その分費用もそれなりにかかります。
また、通塾の回数が限られているため、教室で学んだことを家庭でもう一度振り返るなど、活用の仕方によって効果が変わると感じました。



費用は授業内容を見ると納得でした
理科が好きになるきっかけは「体験」だった
理科の楽しさは、自分で手を動かしたことが頭に残り、そこから発展して考えられることにあるのかもしれません。
驚いたことや感動したこと、実際に目で見たり触ったりしたことは、あとからでも思い出しやすく、テストの場面でも役に立つようでした。
通塾が難しいご家庭でもオンライン塾を利用したり、夏休みの短期イベントなどで理科実験を体験できる教室や地域のイベントもあります。



気になる方は、そういったものを探してみるのもいいと思います。










コメント