 かなえママ
かなえママ解き方は合ってるのに、どうしてこんなに点が取れないの?
中学受験の模試で、わが家が何度も感じた悩みです。
解き直しをしてみると、「なんでこんな間違いするの?」っていうミスばかり。
数字を写し間違えたり、書いた数字が違っていたり、引き算もあやふやで、何度も頭を抱えました。
特に大問1のような計算問題は、配点が30点と高い学校もあり、計算問題を落とすと合格にはつながりにくくなります。
算数は、全ての問題に計算があることから、計算ミスは致命的です。
今回は、計算ミスに悩んだわが家が、実際にやってみてよかったことと、覚えておいて助かった計算パターンを紹介します。
算数塾で言われた「覚えるべき計算」とその効果
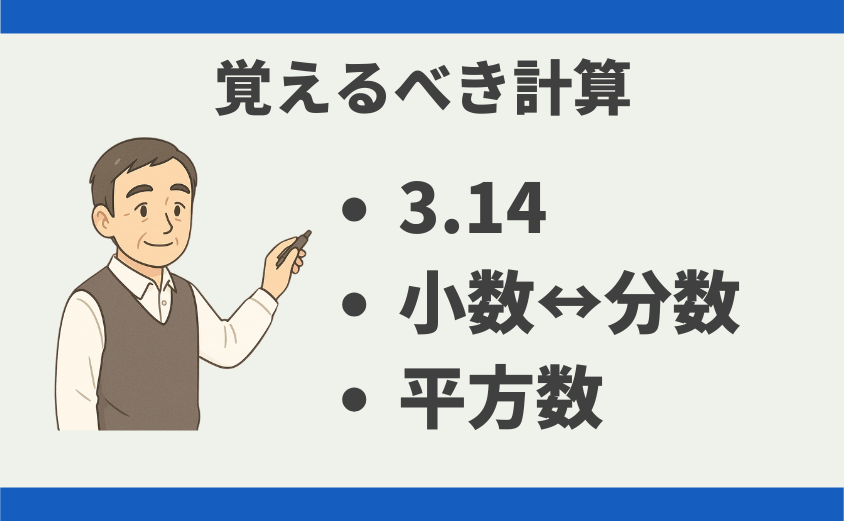

わが家では、大手塾を5年生の前半でやめたあと、算数だけは1対1の個別指導の算数塾に通っていました。※大手塾をやめた経緯については、別の記事で詳しく書いています。
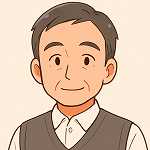
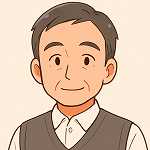

計算ミスを防ぐには、3.14や小数↔分数、平方数などの計算は暗記
この算数塾では、「この3つは暗記です」と言われて、その通りに覚えました。
毎回、算数塾に着いたらすぐにその3つの計算だけ何度もプリントテストされました。
覚えたことで、暗算で済む計算をわざわざ筆算して時間をかけたり、数字を写し間違えたりすることも減っていきました。
試験本番は、時間は限られているので「ゆっくり慎重に計算すればミスを防げる」というわけにはいきません。
だからこそ、試験が近づいてからは、1行問題を1問2分以内で解くことを意識して、時間を計って解く練習も取り入れていました。
※1行問題を「1問2分以内で解く」と決めていた理由については、別記事で詳しく書いています。
中学受験で覚えておきたい計算一覧(3.14・分数・平方数)
3.14の掛け算
2 × 3.14 = 6.28
3 × 3.14 = 9.42
4 × 3.14 = 12.56
5 × 3.14 = 15.7
6 × 3.14 = 18.84
8 × 3.14 = 25.12
9 × 3.14 = 28.26
12 × 3.14 = 37.68
15 × 3.14 = 47.1
16 × 3.14 = 50.24
25 × 3.14 = 78.5
36 × 3.14 = 113.04
小数と分数の対応(換算用)
1/2 = 0.5
1/5 = 0.2
1/4 = 0.25
3/4 = 0.75
1/8 = 0.125
3/8 = 0.375
5/8 = 0.625
7/8 = 0.875
平方数の暗記(11〜19まで)
11 × 11 = 121
12 × 12 = 144
13 × 13 = 169
14 × 14 = 196
15 × 15 = 225
16 × 16 = 256
17 × 17 = 289
18 × 18 = 324
19 × 19 = 361
計算の工夫に関する本の紹介
計算の工夫に関する本もいくつか出版されています。
気になる方は、一度中身を確認して、子どもに合いそうかどうか見てから判断してみてもいいかもしれません。
まとめ:計算ミスを減らすには、よく出る計算を覚える
先生に「これは暗記です」と言われた3.14や小数↔分数、平方根などの計算は覚えました。
どこで計算ミスをしているのか、どんな計算でつまずいているのかは、子どものやり方を横で見ていたからこそ気づけたことでした。
ミスの傾向が見えてきたことで、算数塾の先生に相談するきっかけになり、覚えておいた方がいい計算を教えてもらえました。
他には特に何もしてないけど、この3つを覚えただけで計算ミスが減って、点数も取れるようになってきました。
始めは「これだけでいいの?」って思いましたが、うちには一番合ってたんだと思います。



























コメント