うちの子が算数でつまずいたのは、水溶液の濃度計算でした。
テキストを見ながら教えてみたけど、子どもはちっともわからず大喧嘩はしょっちゅうでした。
 かなえママ
かなえママこんなに何度も説明してるのに、なんでわからないの?
塾のテキストにはビーカー図での解き方が書かれていて、それを見ながら一生懸命説明したけど、まったく通じませんでした。
もしかして、うちの子が理解できないの? でも、テキストに書いてあるのはこれだけなんだけど…。
この記事では、子どもがつまずいた単元をきっかけに、「解法は1つじゃない」と気づけた体験をお伝えします。
別の解法を使えば簡単に解けた
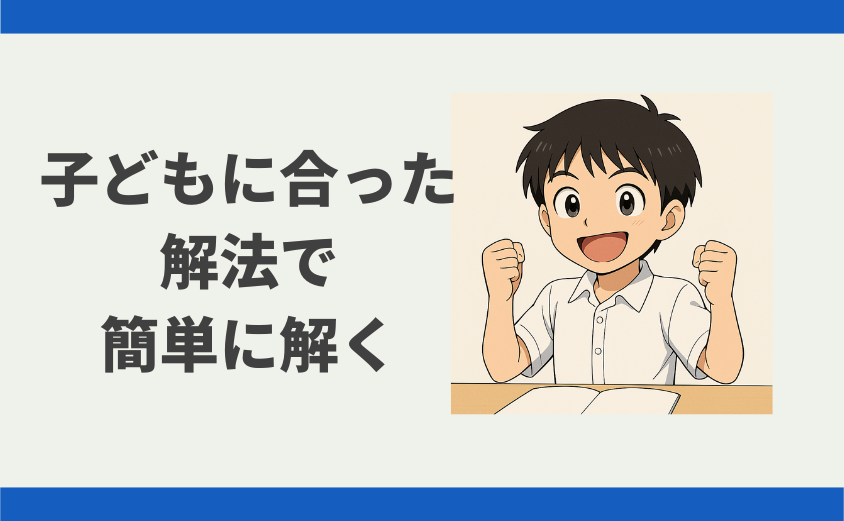




他の解き方はあるの?
塾では他の解き方の方法は教えてくれません。
でも子どもは解けない、私はどうすればいいのかわからない。
やり方が合ってとないのはわかるけど、それ以外を私も知りません。
もう仕方ないのかな、あきらめるしかないのかな…そんな気持ちになっていました。
私自身どうしたよいか困ってしまい、本屋さんに行って見つけたのがこちらの本。
この本には水溶液の計算が塾とは別の方法(てんびん図)で解いてあったのです。
実は私、この本に出合うまで、どの塾でも同じ解法を使って解いていると思っていたのです。
このてんびん図で解く方法はとても簡単なので、ビーカー図で理解できなかった子でもすぐに解くことができました。
うちの場合は、てんびん図で解くのがいちばん速くて、計算ミスも少なかったです。



この本に出合った時は「他の解き方がある(驚)」と衝撃でした
子どもに合う解き方を見つけたら算数が変わった


大手塾は退塾していましたが、この本をきっかけに、うちは1対1の個別指導の算数塾に通い始めました。
そこで気づいたのは、水溶液の解き方だけでも塾によって全然違うということです。
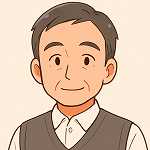
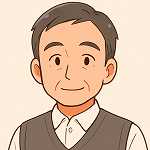

ビーカー図のほかにも、てんびん図や面積図で教えているところもある。つまり、解き方はひとつじゃないということです。
算数塾の先生の話を聞いて、解き方はひとつじゃないんだと初めて気づきました。
先生からは、「好きなやり方を使えばいいんだよ」と言われてそうだよねと思ったのです。
一方で、ある大手塾の先生の話では、「自分が教えていない解き方で答えを出した場合は、不正解にする」というケースもあるそうです。
その塾のその人だけの理不尽なルールというだけで、中学受験本番では正解かどうかがすべてで、どのやり方を使ったかは問われません。
だからこそ、塾のやり方に縛られすぎる必要はないんだなと、強く思いました。
夏期講習と志望校別特訓で通といた塾Aでは、問題演習の中で面積図の解き方がわからず先生に質問したことがありました。
てんびん図なら理解できていると伝えたところ、「てんびん図がわかるならその方法で教えるよ」と言ともらえたので、そのときはてんびん図で解きました。
柔軟に対応してくれる先生もいるんだなと感じたうれしい出来事です。
水溶液だけじゃない、旅人算や鶴亀算も解き方は複数ある
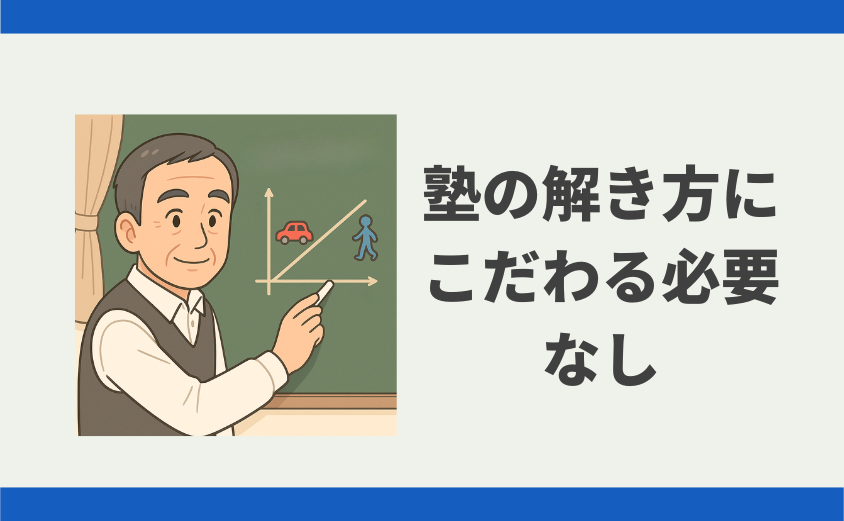

水溶液の問題だけじゃなくて、旅人算や鶴亀算でも同じです。
これらは中学受験でもつまずく子がとても多い単元です。
たとえば旅人算なら、ある塾では線分図で教え、別の塾ではグラフ(ダイヤグラム)を使います。
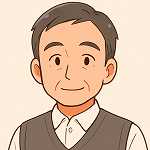
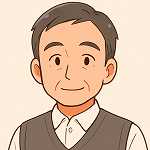

試験中にグラフから描くのはちょっと大変なんだよね
鶴亀算でも、差に注目する線分図のやり方や、いきなり式を立てる方法などがあり、どれが合うかは子どもによって違います。
こういった違いに気づかず、「塾のやり方で解けなければいけない」と思ってしまうことが、一番もったいないのかもしれません。



解法によって苦手意識が出てしまうのは避けたいですね
まとめ:塾の教え方にこだわりすぎないことが大切
最初は「このやり方しかない」と思っていたけれど、実は解き方はいくつもあるんだと気づいてから、わが家の算数は大きく変わりました。
どのやり方が合うかは、子どもによって本当に違うのだなと感じます。
塾のテキストに書いてある方法が合わないと感じたら、別の解き方を試してみてもいいと思います。
最近は、個別指導もオンラインで受けられるようになり、家にいながら相談できるサービスも増えてきています。
たとえば、オンライン個別指導が受けられるまなぶてらす
合わない解き方で悩んでいたとき、他の解法を教えてもらえたことで算数の解き方がぐっと変わりました。
もし今のやり方が合っていないかも…と感じたら、オンラインで相談できる個別指導を活用してみるのもひとつの方法かもしれません。



分からないところだけスポット的に使えるので、一度試してみてもいいですね
























コメント