過去問の解説を見て、「この表ってどこから出てきたの?」「説明これだけ?」と感じたことはありませんか。
私も「この表から〇〇が分かります」「この図を見れば〜」といきなり書かれていて、問題にも書いていない表や図が急に説明に出てきて、「は?」となることがよくありました。
問題文が長いのに、解説はほんの数行。
「え、これだけ?とてもじゃないけど分からない」と、思っていました。
過去問の解説が省略されるのはなぜ?
わが家がお世話になっていた算数塾の先生は、過去問の解説を作ったことがある方でした。
その先生が教えてくれたのは
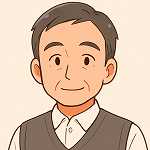 算数塾の先生
算数塾の先生過去問の本で削れないのは入試問題、削ってもいいのは解説なんです。
入試問題は削ることができないので、決められたページ数の中に各教科の問題をすべて収める必要があります。
そのため、解説に割けるページ数はどうしても限られていて、図や式、思考の途中過程などが省略されてしまうことが多いそうです。
つまり、過去問の解説が分かりにくいのは、物理的にそうならざるを得ないことが多いということなんです。
解説が塾のやり方と違っていても大丈夫
1つの単元でも複数の解き方が存在するということは珍しくありません。
わが家の場合、水溶液の濃度計算の問題は、最初に大手塾で計算式を使って解く方法を教えてもらいました。
そのあと算数塾に通うようになって、比(てんびん図)を使うと楽に解けるよ、と言われて、その方法で解くようになりました。
でも過去問の解説には、そのうちのどれか1つの解き方しか載っていないことが多く、塾で教わった方法と違うやり方が書かれていると、「どうすればいいの?」と戸惑ってしまうこともあります。
そして親の側も、授業を受けていないために、「この解説に書いてあるやり方が、塾で習った方法なんだろう」と思い込んでしまいがちです。
だからつい(怒りに任せて)よく言っていた言葉があります。



これ習ったでしょ。も~…ちゃんとやってよ
でも、本に載っているのは、あくまで「この問題を解いた人のやり方」であって、すべての方法が網羅されているわけではありません。
解き方が違う、解けないと感じたら、塾の先生にやり方の確認をするのが一番早くて確実です。
無理にその解説を理解しようとするより、「今、自分が慣れているやり方」で進めたほうが、スムーズに力がついていきますよ。


中学受験 解説が分からない時の勉強法と対策
解説が分かりにくかったり、塾のやり方と違っていたりすると、子どもだけで解決するのはとても難しいものです。
だからこそ、家庭でどうサポートするか、分からなかったときにどう動くかが大切になります。
まずは親が一緒に読んでみて、理解できればその場でサポートしてあげればOK。
解説を言いかえたり、ポイントをかみくだいて伝えてあげるだけでも、子どもには十分伝わることがあります。
塾の先生に聞くのがいちばん確実
解説がわからない問題は、塾の先生に聞くのが一番早いです。
問題を持って先生のところに行き、直接解き方を教えてもらえると安心です。
もし「こうやって解いたけれど、この先が分からなくなった」といった流れが少しでも話せると、先生のほうでも、お子さんがどこでつまずいているのかが分かりやすく、対応しやすくなります。
また、その問題が解けないということは、その単元自体にあいまいな部分がある可能性もあります。
似たような問題でもまたつまずいてしまうかもしれないので、できない → わかった → 解ける → 何度やっても解ける、という状態にしておくことが大切です。
塾以外で聞ける場所も知っておく
家で問題を解いていて「これ、今すぐ知りたい!」と思ったときに、すぐに質問できないことってありますよね。
塾の先生に聞こうとしても、タイミングが合わずに先生が帰ってしまうこともありますし、質問待ちの列が長くて時間切れになってしまうこともあります。
そんなふうにして、結局そのままになってしまうこともあります。
「まあいいか」とあきらめてしまったり、そもそも質問しようと思っていたことを忘れてしまうこともあります。
分からないところが放置されたままになると、小さなストレスが積み重なっていきます。
そんな時のために、塾以外でも質問できる手段を知っておくと安心です。
最近は、オンラインで質問できるサービスも増えてきました。
たとえば、まなぶてらすのようなマンツーマン型のオンライン家庭教師サービスでは、わからない問題を丁寧に教えてもらうことができます。(相談や無料体験も可能です)
塾で聞けなかったときや、すぐに確認したいときの代替手段として活用できるので、知っておくだけでも安心材料になります。
今すぐ使わなくても、「こういう方法もある」と頭の片隅にあるだけで、いざという時に気持ちがラクになりますよ。


まとめ:解説で悩むより、つまずいた単元に早く気づくことが大切
わが家では、算数塾の先生に間違えたところの解き方をすべて教えてもらっていました。
というのも、解説を読んでもよく分からないことが多かったからです。
だから、1回読んで分からなければ、それ以上悩まずに先生に聞くようにしていました。
解けないということは、その問題だけじゃなく、その単元全体が理解できていないこともあります。
そのため、なるべく早い段階で「分からないところ」をクリアにしておくことを大切にしていました。
過去問の解説は、読んで分かるならそれでもいいけれど、分からないまま時間をかけるくらいなら、聞いた方が早くて確実です。
つまずいたときに、親が一緒に確認する、塾の先生に聞く、それが難しければ、塾以外で聞ける場所を知っておく。
悩みをため込まずに、「分からなかったらすぐに動く」を繰り返していけば、理解できるところが少しずつ増えていきますよ。








コメント