中学受験が本格化してくると、「過去問っていつから?何回解けばいいの?」と気になる方も多いと思います。
わが家では、5年生の春に集団塾をやめてからは、算数だけ1対1で見てもらうスタイルに切り替えていたので、進め方もその先生に相談しながら決めていました。(※塾をやめた理由や、その後どう進めたかについては こちらの記事にまとめています)
その先生から「6年生になったらすぐに始めましょう」とアドバイスをもらい、算数や理科の過去問を早めにスタートしました。
実際に取り組んでみてわかったのは「何回解くか」よりも、「できない問題をどうやってできるようにするか」が何より大事だということ。
この記事では、わが家が実践した過去問の使い方・解き直しの工夫・単元別のまとめ方・志望校別の取り組み方まで、体験ベースでまとめています。
 かなえママ
かなえママ初めて過去問に取り組む方のヒントになればうれしいです
過去問は何回解けばいい?「できるようになるまで」が正解
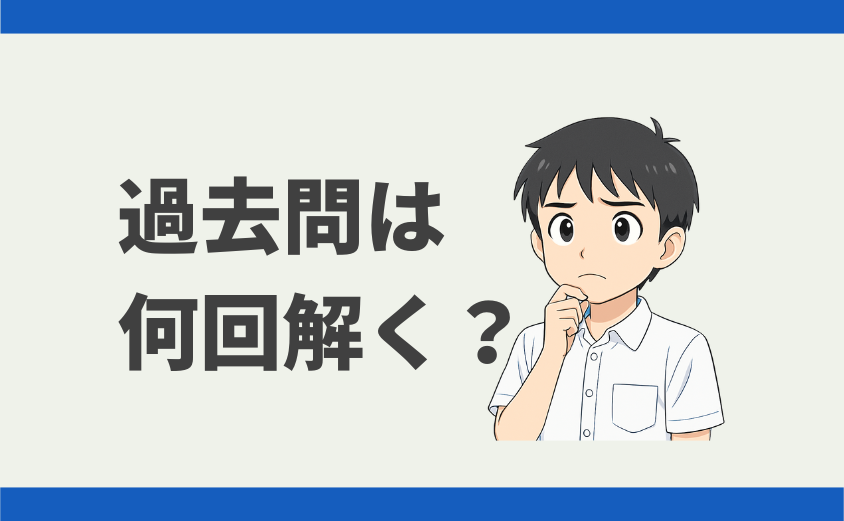

中学受験の過去問、「いつから解き始める?」「何回解けばいいの?」とよく聞かれます。
わが家の場合、塾の先生方に教えてもらった基本の考え方を軸に、効率よく進めることができました。
ここでは、わが家の取り組みと先生からのアドバイスをもとに、過去問の始め方と使い方をお伝えします。
過去問はいつから始める?わが家は6年春スタート
6年生になるタイミングで、算数塾の先生から「過去問はすぐに始めましょう」とアドバイスをもらい、言われた通りに塾にある過去問を解き始めました。
理科についても、同じ先生が計算問題を見てくれていたので、算数と理科は6年の春から過去問に取り組む形になりました。
塾に保管されていた志望校の過去問はすべて解き切る方針で、少しずつ進めていきました。
ちなみに、塾では「過去問は夏から」と言われることが多いですが、それには理由があります。
ひとつは、過去問の最新版が毎年6〜7月に発売されること。
もうひとつは、塾のカリキュラムが夏期講習が始まる前までに受験範囲をひと通り終えるようになっていることです。
つまり、「夏から過去問」というのは、教材が揃うタイミングと、学習内容の一巡がちょうど重なる時期という意味なんですね。



大問1の計算問題は夏を待たなくても解けるので、先に解いてしまうこともできますよ
何回解けばいい?「できるまで」が基本の考え方
中学受験の過去問、「何回解けばいいの?」と気になりますね。
わが家は5年春に通塾をやめていましたが、6年生では塾Aの夏期講習と志望校別特訓だけ参加していたので、必要なときに各教科の先生に質問したり、過去問の進め方を相談したりしていました。
算数塾の先生も、塾Aで教わった他教科の先生方も、そろっ「できない問題ができるようになるまで何度も解く」ということでした。
どの先生も同じことをおっしゃっていたので、これが基本の考え方になりました。
意外だったのは、「〇回解いてください」とは誰も言わなかったことです。
よく「過去問は3回解くといい」と言われることもありますが、大事なのは回数ではなく、できるようになるまで解くこと。
3回解いても解けなければ意味がありませんし、逆に1回でも理解できていればそれでOKです。
わが家でも、解けなかった問題だけを繰り返し解いて、解き方を定着させるというやり方をしています。
何より大事なのは、「間違えた問題の解き直し」です。
その場で解説を見て終わりではなく、自力で解けるようになるまで何度も解き直すことがポイントです。
わが家では、冬期講習やお正月特訓をあえて休むという選択をして、算数塾のみに絞りました。
算数以外の教科については、大手塾の各教科の先生に「過去問の解き方」を1対1でじっくり聞き、その通り実践しました。



〇回と言われるとわかりやすいけど、問題が解けないことには合格に近づかないですよね。
中学受験 過去問の効果的な解き方
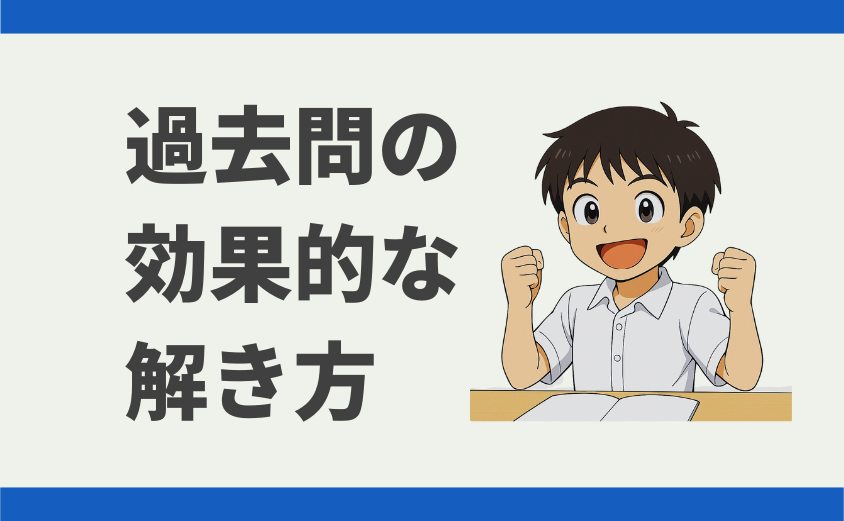

ただ過去問を何度も解くだけでは、なかなか力がつきません。
「どう解くか」「どう繰り返すか」がとても大事です。
わが家が塾から教わった方法は、シンプルですが得点力につながるやり方でした。
STEP① まずは全問を一度解く
まずは、その年度の問題を全問解きます。
このときは時間を測っても測らなくてもOK。
とにかく「今の実力でどこまで解けるか」を見ることが目的です。
間違えた問題は、すぐに解き直し。自力で解き直して正解できるかを確認します。
STEP② 間違えた問題だけを解き直す
次は、1回目に間違えた問題だけを再挑戦します。
1回目で正解していた問題はスキップしてOK。
このときも、解き直してまた間違えていたら再度やり直し、正解できたものは次では解きません。
STEP③ さらに解けなかった問題を繰り返す
1回目、2回目でも間違えた問題だけをもう一度解きます。
このステップでほとんどの問題が正解できるようになりますが、もしそれでも間違えるようであれば、何度でもやり直すのがポイントです。
正解した問題は「確認」だけでOK
解ける問題を何度もやる必要はありません。
「ちゃんと理解できている」と確認できれば、それでOK。
過去問の目的は、「今は解けない問題」を「本番で解ける問題」に変えていくことです。
このステップを繰り返すことで、苦手な単元がはっきりしてきたり、出題パターンに慣れたりします。
ただ回数をこなすよりも、1問ずつ丁寧に解き直すことが得点アップにつながると感じました。



解ける問題を再度解くのは時間の無駄です。解けない問題を解けるようにする時間に使うのが正解!
単元別に過去問を解く方法とコツ


過去問には「年度ごとに解く方法」と「単元ごとに解く方法」があります。
わが家では、単元別にまとめて解く方法をとっていました。
この方法は手間はかかりますが、苦手な単元を集中して克服できるのが大きなメリットです。
単元別 vs 年度別、どちらがいい?
年度ごとに解く方法:10年度→11年度→12年度…と順に解いていくスタイルは試験形式に慣れやすい。
単元ごとに解く方法:計算、速さ、割合…など、テーマ別に問題を集めて解くスタイルは苦手克服に向いている。
どちらが良いかは目的によりますが、「理解を深める」「苦手をつぶす」には単元別の方が効率的だと感じました。
単元ごとにまとめる手順とファイル管理の工夫
わが家のやり方をご紹介します。
- 志望校の過去問題集を全ページコピーする(わが家の場合、キンコーズで背表紙を断裁してコピー)
- コピーしたものを問題ごとに切り、A4の紙に貼る(この時に解き方や答えも問題の下に貼る)
- 単元別に分類(例えば「速さの問題」「水溶液問題」…というようにまとめる)
- 暗記マスターにデータをいれて、iPadで過去問を見ながらノートに解く



志望校の問題だけを集めた、自作の単元別問題集が完成です
詳しいやり方はこちらの記事が参考になります。


わが家の場合、暗記マスターを使うことを前提としていたので、上記の方法にしています。
わざわざiPadに入れないという人は、A4の紙に問題を貼り、回答はそのまま持っておく。
もしくは別の紙に詳しい解き方を書いたものを用意しておくなどすると〇つけが楽です。
この方法は手間がかかりますが、学校の出題傾向や頻出単元をつかむには、とても効果的な方法だと感じました。



作るのは本当に大変でしたが、子どもが解答を見ないで済むという利点もありました
単元ごとに解くメリット・デメリット
単元ごとに解くことで、学校の出題傾向などもわかったのは大きな収穫でした。
わが家の場合、入手できる過去問はすべて解きました。
10年分の過去問が入手できたとして、1単元10問ですから問題数が多いかといわれたら、そこまで多くないと思います。



普段の授業の宿題のほうが解く問題が多いですから、これぐらい解いてもらわないと…ね
志望校別に過去問をどう使う?優先順位の考え方


過去問をどこから解くか迷ったとき、合格したい学校の出題傾向に一番慣れておきたかったので、わが家は第一志望校を最優先にしました。
第一志望校を優先して取り組む
「他の学校の過去問をやる時間がなくなるのでは…?」と心配になるかもしれませんが、第一志望の過去問をしっかり解いていれば、他校の問題もスムーズに解けることが多いと感じました。
実際にわが子も、第一志望の問題に慣れたあとに第二志望以下の問題を解くと、スッと入っていけたことが何度もありました。
また、学校ごとの出題傾向や言い回しにも自然と慣れていくので、最初からすべての学校をやろうと思わずに、志望校ごとに集中して進めるのがおすすめです。
問題の傾向や相性を知るためにも実践的
過去問を実際に解いてみると、「この学校の問題、わが子には合ってる」「ここの算数はクセがあるな」「あれ、国語の問題が全く解けない」など、志望校との相性もなんとなく見えてきます。
入試問題は、その学校の出題のクセがあるので、実際に解いて感触を確かめることも大事です。
気になる学校が複数ある場合、入試問題を解いて解きやすい方に決めるなどの判断が必要になるかもしれません。



問題を作っているのは、その学校の先生です。問題の相性が悪いということは…いろいろ考えちゃいますね
まとめ:過去問を「何回やるか」より「どうやるか」
中学受験の過去問は、ただ回数を重ねるだけではなかなか力になりません。
やっぱり大切なのはできない問題をできるようになるまで解き直すことだと感じました。
最初は「何回やればいいのかな?」と迷うかもしれませんが、わが家の経験では、回数よりもどう取り組むかのほうが大事でした。
- 解けない問題は、繰り返して定着させる
- 解ける問題は、確認するだけでOK
- 得意よりも、苦手に時間をかける
この方法は時間も手間もかかりますが、本番で得点につながる力をつけるには一番効果的だったと思います。



「できるまで解く」を意識して、過去問に取り組んでいけるといいですね










コメント