 かなえママ
かなえママこの塾、本当に合ってるのかな?
そんなことを考えながら、中学受験に向けて子どもを塾に通わせていました。
最初に選んだときは、「ここなら大丈夫」と思っていたけのですが、実際に通い始めると少しずつ違和感を感じるようになりました。
クラス替えがあるたびに環境が変わり、先生の教え方も合わないと悩む日々が続きました。
「転塾?それとも、このまま続けたほうがいいの?」そんな迷いの中で、わが家は退塾を決意し、その後は試行錯誤の日々が続きました。
この体験談が、同じように悩んでいる方の参考になればと思います。
わが家の塾選びとスタート
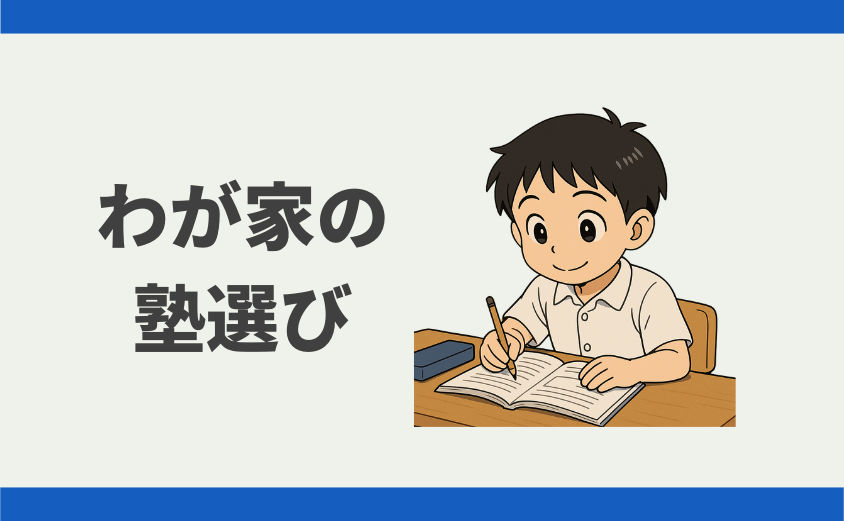

塾に入った当初は中学受験のことは全く考えていませんでした。
もともと公文に通っていましたが、合わなくなったきため別の塾を探すことになったのです。
そのとき、ちょうど近所に低学年向けのクラスを開講している大手塾がありました。
勉強の習慣づけになればいいぐらいの軽い気持ちで入塾。
続けたければそのまま続ければいいし、嫌ならやめてもいいくらいの感覚でした。
低学年のころは生徒の数も少なく、10人ぐらいのアットホームな雰囲気で、特に問題もなく通っていました。
ところが4年生になると状況が一変。塾生の数が一気に増え、クラス分けが行われ、先生も変わりました。
「受験塾になったな」と感じるほど、雰囲気も授業の進め方も変化しました。
先生によってやり方も異なり、慣れるのが大変でした。
4年生から環境が変わり、5年生で大手塾を辞める
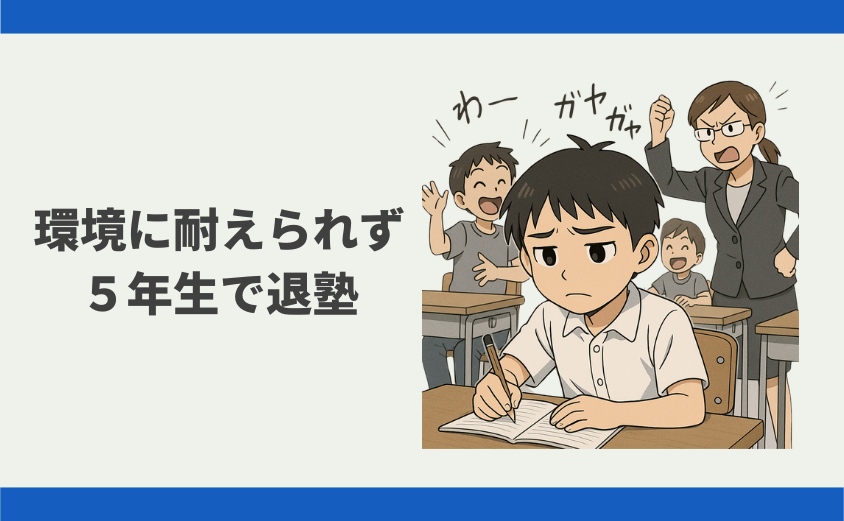

4年生になると、塾でのクラス分けが始まりました。
成績順にクラスが分けられることで、子どもに合ったレベルの授業を受けられると期待していましたが、実際には塾の環境そのものに問題があり、次第に通い続けることが難しくなりました。
先生の対応、教室の雰囲気、クラスメイトの問題行動など。
子どもは塾へ行くのを嫌がるようになり、何度も改善をお願いしましたが、大きな変化はありませんでした。
「この塾ではもう続けられない」と判断し、退塾を決意することになります。
クラス分け後、授業の雰囲気が一変
暫くするとクラス分けにより先生やクラスメイトが変わりましたが、その影響は想像以上でした。
授業の雰囲気が大きく変わり、学習環境が悪化してしまったのです。
特に気になったのは、先生の指導方法です。
担当の先生はベテランの方でしたが、生徒を動物の名前で呼ぶのです。
「おまえは背が高いからカンガルー」「今日はサルは休み?」と、授業中に当たり前のように言うのです。
保護者の前でもこうした発言があり、嫌悪感を覚えました。
このことを校舎長に相談し、一度は注意されたようでしたが、その後は「細かいことをうるさく言う保護者がいる」と嫌味を言うようになり、保護者にも遠回しに皮肉を言うようになりました。
また、別の教科の先生は声が小さく、黒板に向かったまま話し続け、何を言っているのか分からないと言います。
他のお母さんが先生の交代を抗議していましたが、変わることはありませんでした。
教室の騒がしさと授業の質の低下
子どもが「教室がうるさくて先生の説明が聞こえない」と何度も訴えるため、授業を見学させてもらいました。
授業が始まると、クラスの端では「これで合ってる?ねぇ先生これでいいの?」と大声で叫ぶ子がいて、授業中にもかかわらず、落ち着いた学習環境とは程遠い状態なのです。
私自身、この授業を見て小学校の授業の方がよほど落ち着いていると感じるほど。
塾の授業中とは思えない光景に、愕然としました。
後から子どもに聞くと「今日、先生が丁寧だったのは、お母さん(私)が見ていたから」とのことでしたが「これで丁寧な説明だったの?」 と驚きました。
授業見学後、先生から「どうでしたか?」と電話がありましたが、普段とは違う授業を見せられても、返事のしようがありませんでした。
後日、同じ塾に通うママからも「〇〇ちゃんママ(私)が見てたから、先生の態度が違ってたって子どもが言ってたよ」と聞き、やはり、普段の授業とは全く違うことを確信しました。



その子と同じクラスにならないようにと毎回祈っていましたが、ダメでした
繰り返される問題行動と塾の対応
教室の騒がしさだけでなく、授業中の子どもたちの問題行動が放置されていたことも大きなストレスでした。
クラスには問題行動を繰り返す子がいて、前の席の子の椅子を蹴ったり、隣の子の持ち物を勝手に取ったりすることが日常的にありました。
先生が黒板に書いている間に行われるため、授業中にトラブルが起きても気づかれません。
さらに、先生が見ていないことを見計らって、お弁当を食べていることもありました。
この件については何度か塾に相談し、席を離してもらう対応 をしてもらいましたが、それでも行動は変わらず、子どもは次第に精神的に参ってしまいました。
被害を受けている子は他にもいましたが、塾の対応は「席を変える」だけで、それ以上の対策はありませんでした。
退塾を決意した理由
こうした状況が続く中で、子どもは「もう塾に行きたくない」と言うようになりました。
授業中に落ち着いて勉強できない環境が改善されることはなく、先生の指導や教室の雰囲気、問題行動を繰り返す子への対応にも不安がありました。
何度も塾に改善をお願いしましたが、結局のところ「席を離す」という対応しか取られず、根本的な解決には至りませんでした。
「このまま続けても意味がない」 と判断し、退塾を決意しました。成績が理由で辞めるのではなく、塾の環境が子どもに合わないと感じたからこその退塾です。



この塾に固執せず、他の方法を考えた方が良いと判断しました
退塾の手続きとその後
塾を辞めることを決めたものの、退塾の手続きは思った以上に大変でした。
まず、正式に退塾するには 担任の先生との面談 が必要でした。
さらに、授業料の引き落としの関係 もあり、手続きのタイミングを慎重に確認する必要がありました。
もちろん、塾側の引き留めもありました。
「こうすれば成績が上がる」などと説得されましたが、わが家の場合は成績の問題ではなく、塾の環境が合わなかったことが理由 だったので、話は平行線のままでした。



中学受験をするのをやめましたと言えば、それ以上の引き留めはありません
退塾が決まると、それまで普通に接してくれていた先生も急に素っ気なくなり、態度が変わったのを感じました。
また、同じ小学校の子が多い塾だったこともあり、退塾したことがすぐに広まり、「なんで辞めたの?」と何度も聞かれることになりました。
「中学受験どうするの?」と詮索されることもあり、これがかなりなストレスになりました。


退塾後にかかってきた塾の電話
中学受験が終わると、退塾した塾から電話がかかってきました。内容は、「どの中学に合格しましたか?」というものでした。
もう辞めているのに、わざわざ電話をかけてくることに驚きましたが、塾としては、「〇〇中学合格者〇人!」と合格実績を出すために確認したかったのかもしれません。
特に答える義理もないので、「中学受験はしていません」とだけ伝えました。



退塾した後でもこういう連絡があるのか…とモヤモヤしました
算数塾と理科実験教室を中心に学習し、6年生から大手塾の講習を活用


退塾したあとも中学受験はコツコツ続けようと思っていたので、あらためて勉強の仕方を考えることになりました。
受験に必要な算数と理科の勉強方法を見直し
まず、5年生の6月から算数塾と理科実験教室に通い始めました。
算数は中学受験で特に差がつきやすい科目だと言われていたので、できれば少人数で、わからないところを一つずつ丁寧に見てもらえる塾を探そうと思っていました。
偶然見つけたのが、1対1の完全個別指導をしている算数塾でした。
最初から個別じゃなきゃ、と思っていたわけではなかったんですが、実際に通ってみると、子どもにはすごく合っていたようで、安心して通っていました。
小さな個人塾で、先生は大手塾などでも長く教えていたベテランの方。
過去問の解き方だけじゃなく、「この問題はこういう意図で出されてるんだよ」といった話もしてくれて、どんな相談でも親身に聞いてくれるような先生でした。
どの模試を受けるか、どんな学校が合いそうか、そういう相談も全部この先生にしていたと思います。
今はその塾もなくなってしまいましたが、うちにとっては本当にありがたい存在でした。
最近は、こうした1対1の個別指導スタイルの算数塾も少しずつ増えてきています。
たとえば夏井算数塾(算数塾の個別指導)
集団塾が合わなかった子や、算数をじっくり見てもらいたい場合には、選択肢のひとつとして考えてもよさそうです。(メールで問い合わせもできます)
実は、算数とは別に、理科でも少し困っていたことがありました。
うちの子はもともと理科が好きだったんですが、塾の授業が座って聞くだけのスタイルになってから、だんだん苦手意識を持つようになってしまいました。
「これはまずいな」と思って、やっぱり実際にやってみた方が覚えやすいし残ると思って、個人で運営されている理科の教室に通わせることにしました。
この教室のカリキュラムは、6年生の夏休み前に終わるので、最後まで通い続けました。
6年生から模試と大手塾の講習を活用
6年生になってからも、算数塾での学習は続けていました。
算数と理科の計算問題については、引き続きこの算数塾で見てもらっていましたが、受験は4科目なので、国語・社会・理科の暗記分野は、別の方法で補う必要がありました。
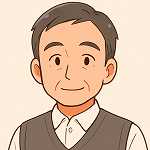
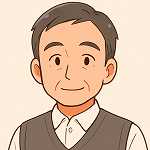

そろそろ4科目を並行して勉強したほうがいいですね
算数塾の先生からのアドバイスで、6年生の夏からは、塾Aの夏期講習と志望校対策講座に参加することにしました。
平日の授業には通わず、講習だけスポットで利用する形でしたが、4科目の全体像を確認しながら志望校の対策もできて、いいバランスだったと思います。
冬休みは塾Aの講習には参加せず、算数塾に戻って学習を進めました。
志望校の算数と理科の過去問対策を中心に、実践的な問題をしっかり見てもらいました。
結果として、講習と算数塾を組み合わせたこのやり方が、うちには合っていたと感じています。



6年の夏休み前まででに塾では一通りの範囲が終了するので、そのタイミングで入るのがベストとの判断でした
6年生夏からの塾の通い方
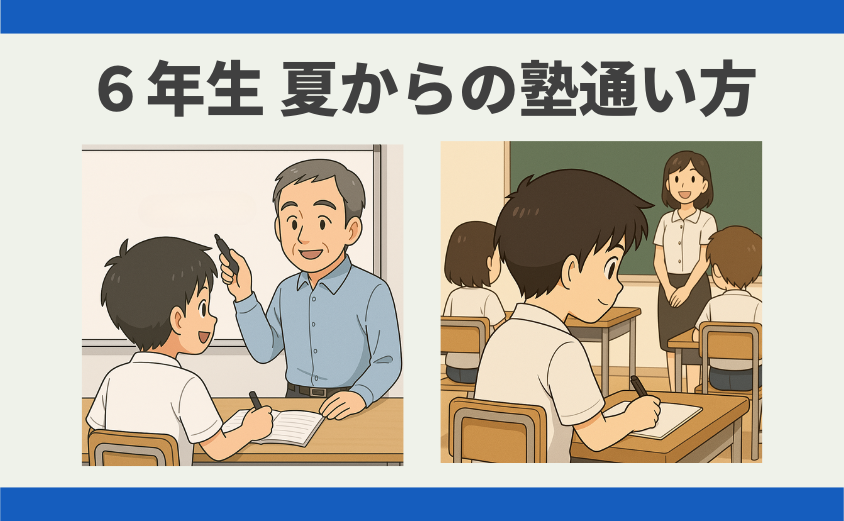

6年生の夏から大手中学受験塾Aに通うことを決めましたが、最初に入塾を予定していた校舎での保護者面談がきっかけで、別の校舎に変えることになりました。
この時に感じた違和感と、結果的に選んだ塾の通い方が、我が家の受験スタイルを決める大きなきっかけになりました。
入塾前の保護者面談での違和感と、校舎変更の決断
最初に入塾を予定していた〇〇校舎で、入塾前に保護者面談が行われました。
面談では志望校を聞かれたので答えると、先生は 「ここの学校の問題はめんどくさいんだよね。解くのも説明するのも嫌なんだ。何人か持ってくるけど、本当に面倒だと思ったよ。」 と何度も繰り返しました。
初対面の入塾者の保護者に対して言う言葉とは思えず、「この先生に教わるのは無理だ」と直感的に感じました。
〇〇校舎は小規模な校舎だったため、先生の数が限られていました。
この先生が担当になる可能性が高いことを考えると、ここで授業を受けるのは難しいと判断し、別の校舎を検討しました。
変更先として考えた□□校舎は規模も大きく、雰囲気や先生の評判も事前に聞いていたので、「ここなら大丈夫かも」と安心できました。



後になって思い出したのですが、退塾した塾でも校舎変更をする子は多かったです。
例えば、算数の先生が好きで、その先生が別の校舎に異動したため、一緒に移った子もいましたし、志望校の合格実績が良い校舎を選んで移った子もいました。
「校舎変更=何か問題があったから」ではなく、より良い環境を求めて移ることは普通にあるのだな、と後になって実感しました。
6年生の夏からの塾の通い方
6年生の夏期講習から、□□校舎での学習をスタートしました。
ただし、通ったのは 夏期講習や志望校特訓などの〇〇講習のみで、平日の通常授業は受けませんでした。
塾側からも「フルで通ってください」と言われることはなく、講習のみの参加でも問題なく受け入れてもらえました。
□□校舎は大規模な校舎で、自宅からもちょっと離れていたので、同じ小学校の子もいませんでした。
そのため、人間関係のストレスもなく、のびのびと通うことができました。
また、保護者会や保護者面談にも参加でき、最終的な志望校を決める際にも相談に乗ってもらえ、、サポート体制も十分、とても頼りになりました。
冬休みは□□校舎の講習には参加せず、算数塾に通いました。
志望校の算数・理科の過去問対策を重点的に行い、入試に向けて実践的な問題演習を進めました。
その後、無事に中高一貫校に合格。
結果として、季節講習と算数塾を組み合わせたこの学習方法が、うちの子には合っていたと感じています。



冬期講習に行かなくてもサポートが変わらなかった□□校舎の先生に感謝しています
塾選びを経験して分かったこと
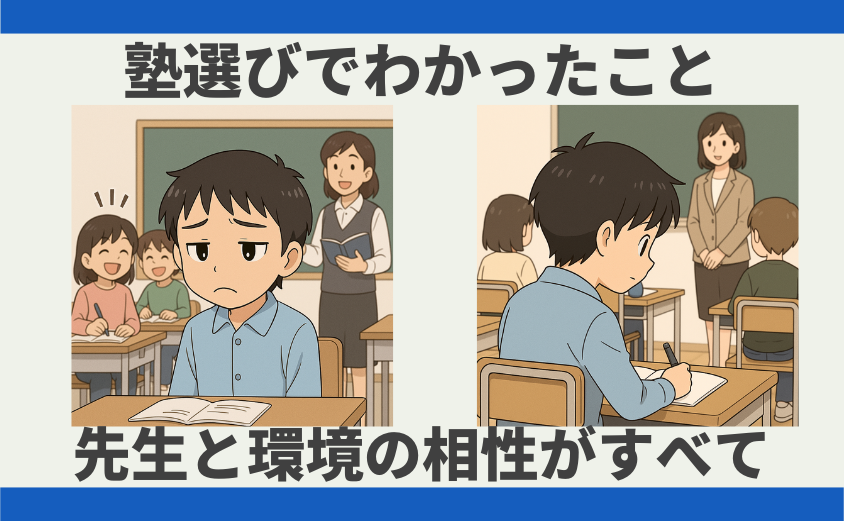

塾選びは、実際に経験してみないと分からないことが多いと実感しました。
低学年のうちは問題なく通えていても、学年が上がると先生やクラスの雰囲気が変わり、状況が一変することもあります。
塾を選ぶときには考えていなかったことに直面し「塾は入ってみないと分からない」 と思いました。
どの塾に通うかの判断は簡単ではありませんが、結局のところ「子供に合った環境を見つけることが何より大事」だと感じました。
「このままでいいのか?」と迷ったら、一度立ち止まって考え、必要なら思い切って環境を変えるのも一つの選択肢だと思います。
私の結論は、塾選びは先生と環境の相性がすべて
塾選びのときは、「とりあえず家から近いし、低学年向けのコースもあるから」と軽い気持ちで決めました。
でも、実際に通ってみないと分からないことが多かったです。
4年生からクラス分けが始まり、先生が変わると授業の質も変わる。
これは最初の塾選びのときには考えていなかったことで、クラス替えのたびに子どもの学習環境が大きく変わってしまいました。
また、塾の雰囲気や先生の対応も、実際に入ってみるまで分からないことの一つでした。
先生の教え方は統一されておらず、分かりやすい先生とそうでない先生の差が大きい、クラスの雰囲気や先生との相性が合わなければ、どんなに頑張ってもどうにもならないこともあります。
「運が悪かった」と思えばそれまでですが、結局のところ、塾選びにおいて相性はとても大切なのだと、このとき実感しました。
でも、どんなに情報を集めても、実際に入ってみないことには合うかどうかは分かりません。
いくら大手塾でも、すべての子どもに合うとは限らない。
結局のところ、塾は実際に通ってみないと合う・合わないは分からない のだと実感しました。



同じ勉強をするにしても、相性はやはり大切だと痛感しました
子どもに合う勉強方法に切り替えて正解だった
退塾するときは、「本当にやめてしまっていいのか?」 そして、「この先、どうやって勉強していけばいいのか?」 と考えました。
でも、結果的に退塾したことで勉強環境が変わり、良い方向に進んだ と思っています。
個人塾に通って算数を強化できたし、最終的には大手塾の講習に参加して受験対策を進めることができました。
そのおかげで、無理なく学習を進められるようになり、過去問対策もしっかりできた ので、合格につながったと感じています。



退塾して別の学習方法を選んだことは、正しい選択だったと思っています。
よくある質問
よく聞かれた質問をまとめました。
- 退塾理由は?引き止められない?
-
わが家の場合、大手塾の環境の悪さ(先生への信頼が無くなった、生徒が授業中にも騒がしい、意地悪をする)など、複数の要因が重なり、塾を辞めました。
引き留めもありましたが、退塾の日付を長引かせないために「中学受験することを辞めました」と伝えることで、それ以上の言われることはありませんでした。
- 退塾の時には菓子折りなどを持っていきましたか?
-
わが家の場合、退塾時に菓子折りなどは持っていきませんでした。
最後に「今までありがとうございました」という挨拶だけはしました。
- 塾を辞めた後のことを考えてから退塾しましたか?
-
塾を辞めると決めてから「退塾する」と伝えるまでの時間が短かったので、後のことは何も考えていませんでした。
実際は授業料の引き落としの関係で、1か月近く大手塾に通うことになってしまいました。
その間に、子どもにとってよさそうな選択肢は何かと考え、たどり着いた答えは「大手の集団塾は選ばない」でした。
わが家が退塾する理由を考えると同じような集団塾はリスクが高いと判断し、最終的に選んだのは1対1の個人の先生が行っている個別算数塾でした。
ピンとくる塾が近くにない、通うのが大変な場合には、オンライン家庭教師のまなぶてらすなどがあります。
無料体験もあるので、中学受験に対応できる相性の良い講師を探すこともできますよ。



5年生の時に大手塾を辞めてよかったと思っています。
まとめ:わが家の塾選びとその結果
どの塾がいいかよりも、「その子が無理なく学び続けられる環境」をどう作るかが大切だと感じました。
塾を選ぶとき、先生との相性やクラスの雰囲気は入ってみないと分かりません。
「この塾なら大丈夫」と思っても、通ってみると意外なところで合わなかったりすることもあります。
だからこそ「この子にとってベストな学習環境はどこか?」 という視点が必要です。
私の場合、塾以外にもアプリを活用し、子どもに合った学習環境を試行錯誤していました。
無料アプリも便利ですが、子どもに合っていなければ意味がない と感じることもありました。
そこで、自分で工夫して、子どもに合う学習ツールを作ることもありました。
塾選びに迷ったとき、「塾に通うこと」だけにとらわれず、「子どもが前向きに学習できる環境をどう作るか?」 を考えることが大事だと痛感しました。



大手塾以外でも、勉強環境があっていればぐんぐん伸びます。














コメント