 かなえママ
かなえママ国語は日本語なんだから、いつかできるようになるでしょ?
そう思っていましたが、甘かったです。
選択肢問題は「なんとなく」で選び、長文問題になると何が言いたいのか分かりません。
記述問題もとりあえず書くものの、的外れなことを書いてしまうことが多く、どうすればよいのか悩んでいました。
塾を辞めたことで、国語の対策はすべて家庭で進めることになったのです。
とはいえ、何から手をつければいいのか分からず、手探り状態が続きました。
いろいろ試した結果、わが家で効果があったと感じたのは論理エンジン・出口の小学国語・ブンブンどりむ・ヨウヤクモンスター の4つの教材です。
それぞれどんな教材で、どう役立ったのか。わが家の体験談をもとに詳しく書いていきます。
国語対策を始められなかった理由
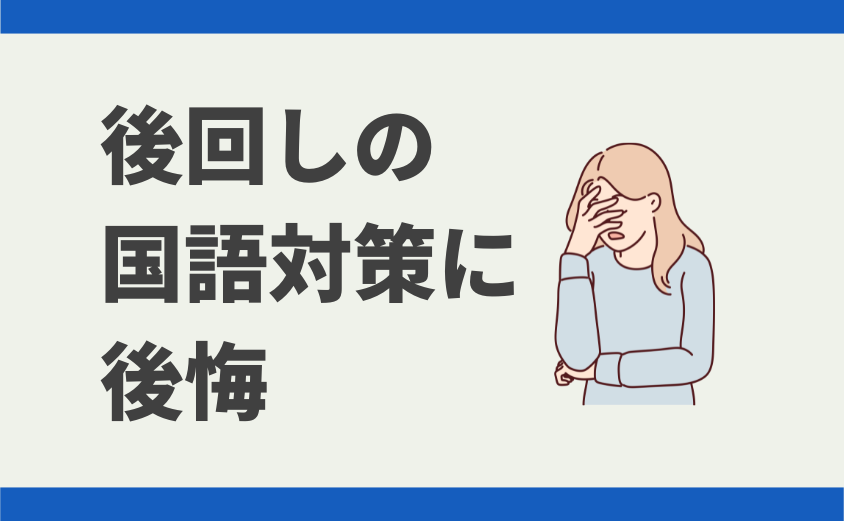

塾を辞めて、国語対策は家でやるしかないと分かっていました。
でも、実際には 半年以上手をつけられずにいたのです。どうしてもできなかった。
何をどうすればいいのか分からなくて、後回しにしてしまったんですよね。
ことわざや四字熟語は「やればできる」し、点数にも直結する。
でも、読解力ってどうやって測ればいいの?どう伸ばせばいいの?それが分からなくて、モヤモヤするばかりでした。
それに、私は塾の先生でもなければ、国語を専門に勉強していたわけでもありません。
子どもの解答を見ても、「これ、100%正しい?」と自信をもって言えないことも多くて、結局どうやって教えればいいのかも分かりませんでした。
そんな状態で、なんとなく時間だけが過ぎていきました。
でも、5年生の後半になって「本当にまずいかもしれない」と焦りが大きくなり、ようやく動き始めました。



現実と向き合う覚悟を決めました
まずは何ができていないのかを見極めた
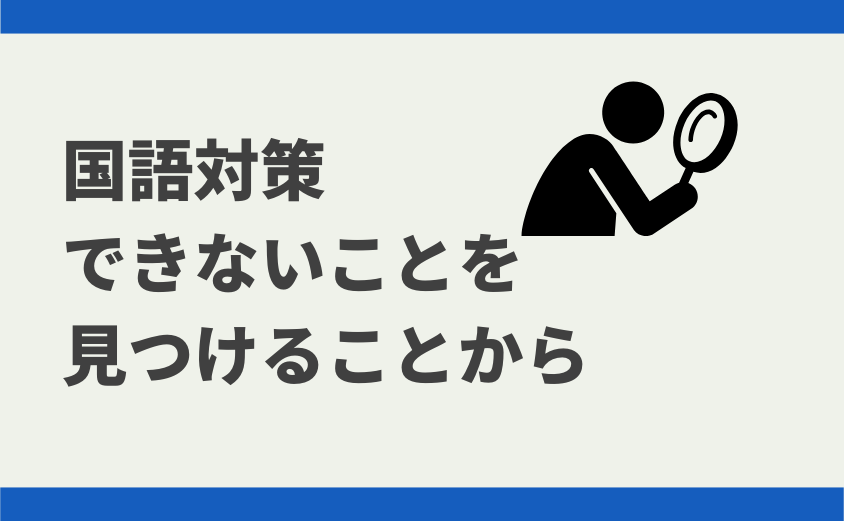

まずやったのは、「この子は何ができていなくて、何ができるのか?」をはっきりさせることでした。
テストを見返してみると、漢字は苦手なところがあるけれど、や四字熟語、ことわざといった問題は大丈夫。
でも、説明文・物語文の読解問題や記述問題になると、一気に点数が落ちている。
これはもう、国語の知識が足りないのではなく、文章を読む力が足りないんじゃないか?と感じ始めました。
でも、それが分かったところで、どうすればいいのか?悩んだ末、できないことを潰していくしかないという結論になりました。
ここで、初めて「国語対策を本格的にやるしかない」と腹をくくりました。



私も子どもとバトルになるのが嫌で逃げてたんですよね。限界まで先延ばしにしていたのです。今思えばバカだったなって思います。
試してよかった国語対策の教材4選
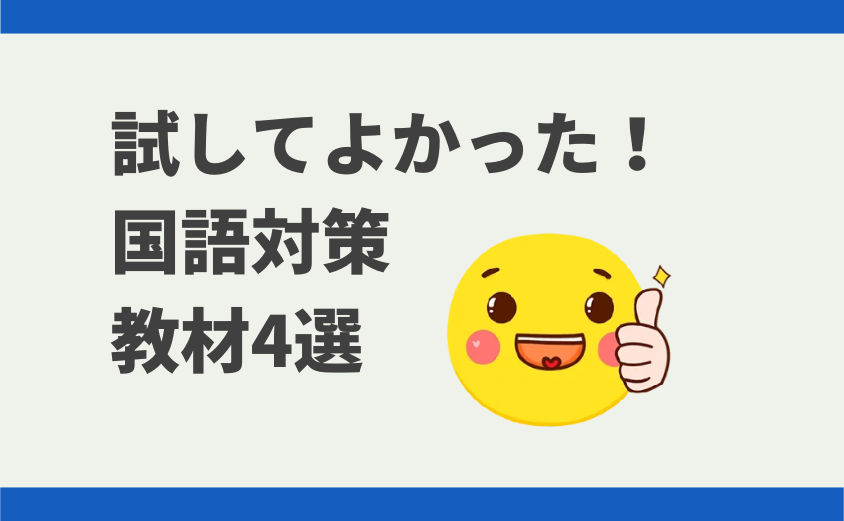

塾を退塾していたため、国語対策は家庭で進める必要がありました。
最初は問題集を解くだけで何とかなると思っていましたが、思うように成績が伸びず、「そもそも文章を読む力を鍛えなければいけない」と気づきます。
そこで、読解の基礎・演習・要約・作文 の4つの分野に分けて対策することにしました。
実際に試してみて、わが家で効果を感じたのが、論理エンジン・出口の小学国語・ヨウヤクモンスター・ブンブンどりむ の4つの教材です。
それぞれの教材をどう活用し、どのように役立ったのか。体験談を交えながら詳しく紹介していきます。
読解の基礎を固める「論理エンジン 小学生版」
「論理エンジン」は、文章の構造や論理的な読み方を身につけるための教材です。
わが家では、国語対策をどうすればいいのか分からず、書店に何度も通って、いろいろな教材を手に取っていました。でも、どれがいいのかピンとこなくて…。
そんな中で調べていくうちに、「論理的な読解力を鍛える教材がある」と知り、これなら「読み方そのもの」を見直せるかもしれないと思ったんです。
書店で実物を見て、「これでやるしかない」と思い切って、1年生から6年生までの全学年分を一気に購入しました。
どこから始めるべきか迷った末、とりあえず1年生レベルからスタート。
この時点で、すべてやり切るには65日かかることも分かっていて、「2ヶ月…本当にこれで間に合うの?」と不安しかありませんでした。



でも、やらないことには何も変わらない。私も必死でした。
国語ができない理由を見つけるためには、ここから向き合うしかなかったんです。
「なんで1年生?」と不満げな子どもを、「簡単ならすぐ終わるから」と説得してスタート。
実際、3年生あたりから音読につまずき、「ここに出てくる〇〇って知ってる?」と聞くと「知らない」と答えることが多く、読めないのではなく語彙が足りていないことに気づきました。
わが家では1日1レベルずつ、音読→言葉チェック→問題→丸つけの流れで習慣化。
すぐに変化は出ませんでしたが、とにかく続けることを大事にしていました。
実践演習に「出口の小学国語レベル別問題集 0~3」
「出口の小学国語レベル別問題集」は、中学入試の過去問をもとにした演習問題集です。レベル0(理論編)からレベル3(難関編)までの4段階に分かれており、基礎から実践問題へとステップアップしながら進められる構成になっています。
国語の実践力を鍛えるのに適した教材ですが、レベルが上がると難易度が一気に上がるため、子どものペースに合わせて進めることが大切です。
わが家では、レベル0(理論編)とレベル1(基礎編)は問題なく解けましたが、レベル2(標準編)に入るとつまずくことが増えてきました。
書くこと自体はできるものの、間違いが増え、正答率は50%ほど。レベル3(難関編)になると、1〜2問解いただけで「もう無理」となり、完全に手が止まってしまいました。
記述問題を解き直しをしようと答えを見ても「へー、そういうことね」で終わってしまい、子どもは自分の答えが正しいかどうかを判断するのが難しかったのです。
数学なら「正解!」と明確に分かりますが、記述問題はそうはいきません。
「どこまで合っているのか」が判断しづらく、答えを見て納得するしかないという状況でした。



レベル2,3はチャレンジしただけでも偉いと思いました。
要約力を鍛える「ヨウヤクモンスター」
「ヨウヤクモンスター」は、文章を要約する力を鍛えるRPG形式の学習アプリです。ゲームを進めながら文章の要点を抜き出していく構成になっていて、楽しみながら「大事な部分を見抜く力」を身につけられるのが特徴です。
わが家の子どもは、要約がとにかく苦手でした。
最初は要約の問題集を使って練習してみましたが、全く解けず、何度やっても上達する気配がありません。
どうやって勉強すればいいのか分からず、「ほかに試せる方法はないか?」と考えたときに見つけたのが、このアプリでした。
正直なところ、「これでダメならもう仕方ない」という気持ちで始めたのが本音です。
国語は、算数みたいに「前は5問しか解けなかったのが、今は10問解ける!」みたいに目に見えて成長を感じられるものじゃないのですよね。
でも、やり込んでいくうちに、少しずつ「あれ?なんか分かるかも?」という感覚が増えていきました。
言葉で説明するのは難しいけれど、「この部分が大事なんじゃないか?」という肌感覚がつかめるようになり、以前よりスムーズに答えを選べるようになったんです。
特に、紙の問題集では時間がかかりすぎていた要約練習が、アプリだとスムーズに進み、解ける問題数が格段に増えました。
選択式でどんどん進められるため、苦手意識があった子どもでも取り組みやすく、負担を感じずに続けられたのもよかったです。



これは子どもにバッチリはまりました。時間を忘れて親子で楽しくできたのは本当によかった
我が家のヨウヤクモンスター体験談はこちら↓


作文嫌い克服に「ブンブンどりむ」
「ブンブンどりむ」は、小学生向けの作文通信教育講座です。作文を書くことに慣れることを目的とした教材で、毎月届くテキストに取り組むことで、表現力や文章の構成力を鍛えることができます。
わが家では、子どもが作文を書くのを苦手にしていたため、「とにかく書くことに慣れたほうがいい」と考え、ブンブンどりむを選びました。
通信講座の教材ですが、キャラクターが登場するカラフルなテキストなので、作文が苦手な子でも取り組みやすい内容になっています。
実は、最初はZ会の作文専科と迷いました。でも、子ども自身が「マンガキャラがいるほうが楽しく学べそう」と言ったので、最終的にブンブンどりむに決めました。
毎月届く教材に沿って作文を書き、添削してもらう流れです。
添削の先生がとにかく褒めてくれるので、「作文、嫌い!」と言っていた子どもも、意外と続けられました。
劇的に作文が得意になったわけではありませんが、「何を書けばいいか分からない」と考え込むことが減り、白紙で提出することがなくなったのは大きな変化です。
とりあえず書き始めることができるようになり、作文への抵抗感も少しずつ薄れていきました。
\無料体験キット申込・入会申込はこちら/



初めは1文字も書けなかったけど、続けていくうちにスラスラ書けるようになりましたよ。
我が家のブンブンどりむ体験談はこちら↓
読む力が、すべての教科の土台だった
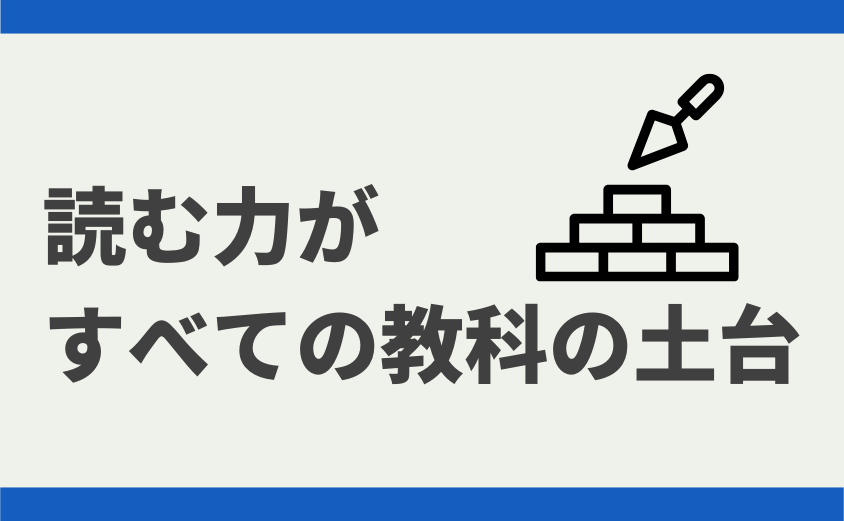

あとになって気づいたことですが、国語の問題だけじゃなく、算数の文章題や理科の記述問題も「文章が読めていなかったから解けなかった」んだと思います。
たぶん、問題で聞かれていることがちゃんと理解できていなかったのは「この言葉は何を指しているのか」「何を求めているのか」がつかめていなかったのです。
文字が読めているように見えても、その意味がちゃんと理解できていない。
だから、どの教科にも共通して、文章の意味を読み取る力=読み解く力 が必要だったんだと感じています。



もっと早く対策していたら、親子とも苦しむ時間が少なくて済んだかもしれません
読解力のない子は、算数や理科の問題も解けない
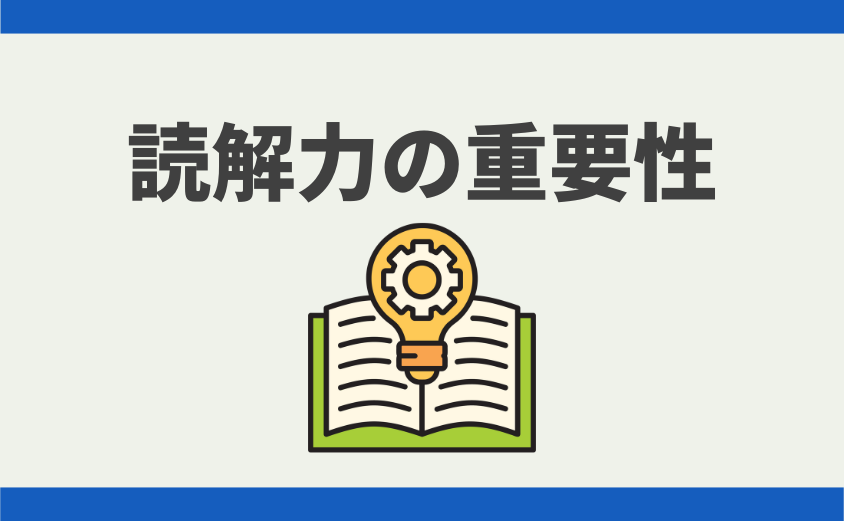

以前、算数塾の先生がこんな話をしてくれたことがあります。
「りんごが3個、みかんが5個あります。全部でいくつですか?」 こういう問題は解ける。
しかし「りんごとみかんがそれぞれ3個あります。全部でいくつですか?」 になると、何を聞かれているのか分からなくなってしまう子がいるのですよ。
数字の情報は同じなのに、言い回しが少し変わっただけで理解できなくなる。
これは、ただ読解力が足りないというより、言葉の意味をとらえる力、文の構造を理解する力が足りていない状態なんですよね。
こういう子は、文章を読んでいるようで、実際には数字だけを拾って計算している。
つまり、教科としての算数が苦手なのではなく、そもそも「問題文の意味が取れていない」というケースもあるんです。



国語を先にやらなきゃいけない理由は、たぶんこういうことなんだと思います
プロ家庭教師に相談するという選択肢も
教材を試しながら手探りで進めていた当時は、「これで本当に間に合うのかな」「今のやり方で大丈夫なのかな」と、焦りと不安だらけの日々でした。
誰かに相談できていたら、もっと早くから動き出せていたかもしれないし、それだけでも安心感があっただろうなと今では思います。
今なら、単発で使えるオンライン家庭教師サービスもあります。
「どこができていないのか、自分では見極められない」というときに、中学受験に対応したプロ家庭教師に、ピンポイントで相談できるサービスがあるというのは、とても心強い存在だと思います。
「まなぶてらす」なら、入会金なしで1回から受講でき、塾をやめたあとや、勉強の方向性に迷ったときの確認用としても使いやすいと感じています。
まとめ:わが家の国語対策は、“今できないこと”を一つずつ潰していく毎日だった
実際に動き出したのは、5年生の後半です。
「このままじゃまずい」と思いながらも、何から手をつければいいのか分からず、悩みながら始めたのがきっかけでした。
そこからは、どこができていないのかを探して、教材を試して、少しずつできることを増やしていく日々。
論理エンジン、出口の問題集、ブンブンどりむ、ヨウヤクモンスター。
どれも「これが正解」と思って選んだというより、「この子に必要そうなこと」を見つけては、試していった結果でした。
もっと早く始めていたら、別の方法もあったのかもしれません。
でも、あの時間がなかったら、ずっと国語に苦しんでいたと思います。
結局、わが家にとっては、「できない」を一つずつ潰していくことが、一番の近道だったんだと思います。



まずは、どこができていないかを見るところからがスタートかも














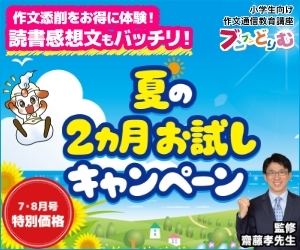













コメント