「中学受験を考えているなら、文化祭に行ったほうがいいよ!」と言われたことはありませんか?
でも、いざ行くとなると…
- 何歳から行けばいいの?
- どんな服装で行けばいい?
- そもそも、文化祭に行くメリットって?
私も最初は「行ったほうがいいのかな?」と迷いましたが、実際に行ってみて、「文化祭は絶対に行ったほうがいい!」と思いました。
パンフレットでは分からない 学校の雰囲気や生徒の様子 がよく見えるからです。
我が家は 小学校3年生から文化祭見学を始めました。
実際に行って感じたこと、見学のポイント、行ってよかったことを 体験談を交えてお伝えします!
中学校の文化祭はいつあるの?
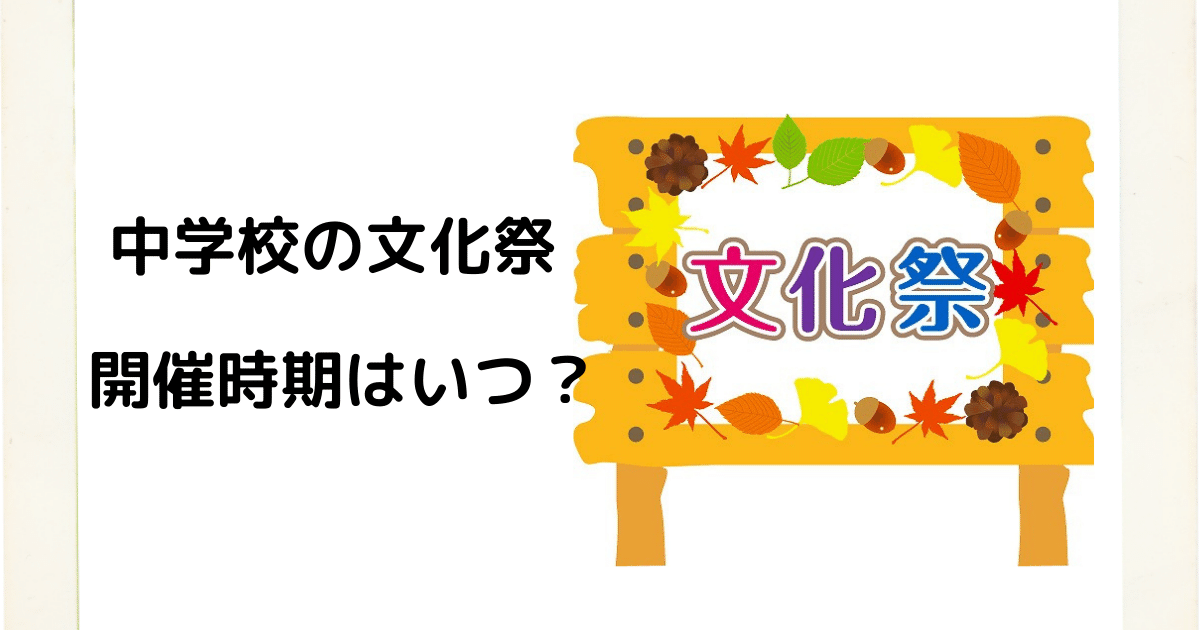
中学校の文化祭は、8月末~11月3日頃までの週末や祝日 に開催されることが多いです。
多くの学校は 2日間開催 され、時間は 午前9時~午後3時~3時半頃まで。
片付けの関係で、午後3時半には終了することがほとんどです。
文化祭と小学校の運動会の日程が被ることも!
我が家の小学校は 運動会が秋開催 だったので、文化祭と日程が重なってしまい、見学に行けなかったことがありました。
「行きたかった学校の文化祭が、ちょうど運動会の日と重なってしまった…!」と残念な思いをしたことがあります。
文化祭は 年に一度のチャンス なので、予定が重ならないように事前に確認しておくのが大切です。
運動会や他の予定と被らないよう、早めにスケジュールをチェックしておくことをおすすめします!
文化祭の日程をチェックする方法
文化祭の日程は、学校のホームページやイベントカレンダー で確認できます。
多くの学校は、公式サイトで事前に文化祭の日程を公開しているので、見学を考えている学校の情報をチェックしておくと安心です。
また、文化祭によっては 「事前予約が必要な学校」 もあるため、詳細を確認しておくのがおすすめです。
こちらのイベントカレンダーで、各学校の文化祭日程を調べることができます!
「気づいたら終わっていた…!」なんてことにならないように、早めにチェックしておきましょう!
中学校の文化祭を見学するメリット・デメリット
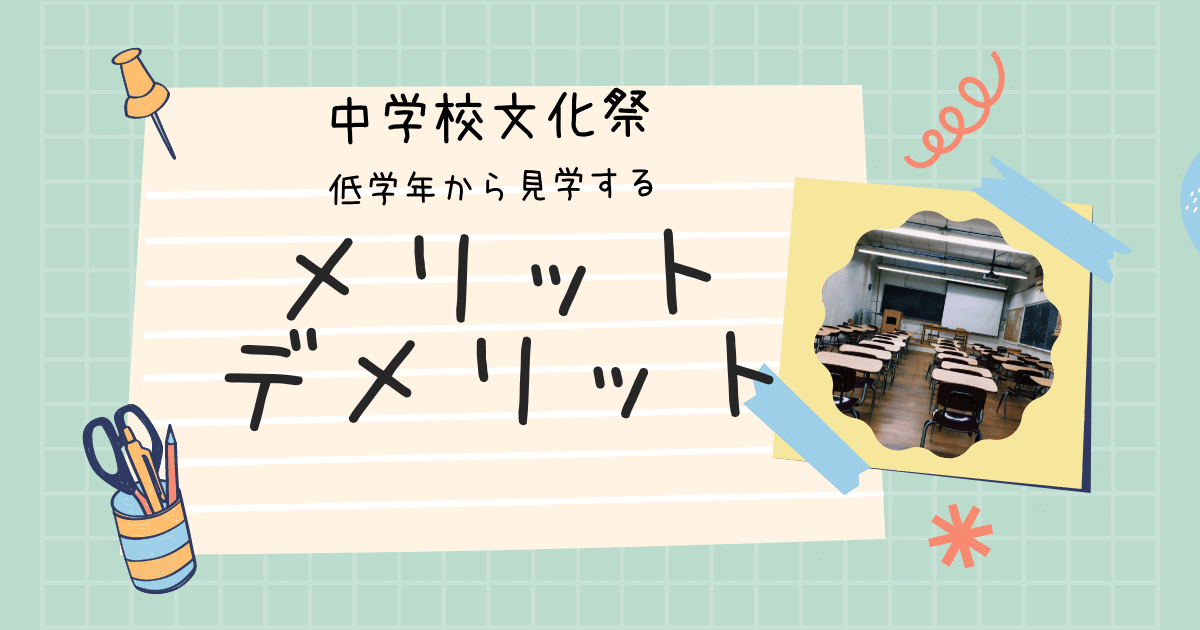
 かなえママ
かなえママ中学校の文化祭って、在校生じゃなくても行けるの?
そう思う人も多いかもしれませんが、ほとんどの中高一貫校の文化祭は、一般の人も見学OK です。
ただし、学校によっては 「受験希望者のみ」「関係者限定」 など、見学できる対象が限られている場合もあります。
そのため、気になる学校の文化祭に行く前に、公式サイトで公開対象になっているか確認しておくと安心 です。
文化祭では、生徒の様子・学校の雰囲気・授業以外の活動(部活・行事)などをリアルに感じ取れる のが大きなメリットです。
また、一度だけでなく、何年か連続で見学すると、その学校の特徴や変化がより深く分かる こともあります。
文化祭に行くきっかけは?
私が文化祭に行くようになったきっかけは、塾のお母さんたちに「早く文化祭に行ったほうがいいよ!」と言われたことでした。
当時、塾の同級生の親たちは、すでに兄弟が中学受験を経験している人が多く、文化祭見学が当たり前のようになっていました。
何歳から文化祭に行く?
塾の先輩ママさんたちに聞くと、「小学校3年生の夏休み明けから行くのがいい」と教えてもらいました。
我が家も、そのアドバイスをもとに、小学校3年生から文化祭の見学をスタート しました。



中学受験経験者のお母さんたちの話を聞くと、こんな理由がありました。
- 1日に何校も行けない(移動時間を考えると、1日1~2校が限界)
- 人が多くて疲れる(特に午後になると大混雑)
- 学校間の移動に時間がかかる(遠い学校だと1日で回るのは大変)
- 文化祭の開催日が重なる(どちらかを諦めることも)
- 校長先生が変わると学校の雰囲気が変わる(毎年見ておくと比較できる)
- 高学年になると塾の模試と文化祭がぶつかるので行けなくなる
このように、「低学年から行くことで、余裕をもって見学できる」 というメリットがあります!
低学年から文化祭に行くメリット・デメリット
低学年(小3~小4)のうちから文化祭に行くメリット・デメリットをまとめました。
デメリットとして2つほど記載してみましたが…実は、そこまでのデメリットではありません。
子供が訪問した学校の印象を忘れてしまうのは、学校に魅力が無かった(刺さるものが無かった)からなのです。
どの学校に行ったらよいのか分からないのであれば、「どこでもいいから行ってみる」のです。
最近では、男子校・女子校が共学校に変わるケース もあり、学校の状況も変わっています。
まず近くの学校へ行ってみる!から始めると頃から始めてみてはいかがでしょうか。



何も考えず「文化祭は楽しい」と思っていけばOK
文化祭に行って何をするの?
文化祭に行く目的は、「パンフレットでは分からない学校の雰囲気を体感すること」 です。
実際に学校を訪れることで、以下のような点がチェックできます。
- 学校までの距離や通学ルートはどうか?
- 先生や生徒の雰囲気は?(フレンドリー?静か?)
- 校舎の雰囲気は?(古い?きれい?)
- 学校全体の活気はどうか?



パンフレットの印象と違うことも。やっぱり自分の目で見ないとね!
文化祭に参加するときの服装
「学校行事なので、普通の格好でいいよ」と、塾の先輩ママさんたちに言われました。
私の場合はニットのアンサンブル+ズボン、主人はボタンダウンシャツ+ズボンです。
学校によって雰囲気は違うものの、どこも 「普段着すぎない程度のきれいめカジュアル」 で問題ありませんでした。
子どもは 小学校に行くときと同じ服装 でOK。
また、文化祭では校内をたくさん歩く ため、スニーカーなど歩きやすい靴がベスト!
体育館やグラウンドに行くこともあるので、脱ぎ履きしやすい靴を選ぶとさらに快適です。



学校内は人多いので暑さ対策のために、脱ぎ着しやすい洋服を選ぶのがおすすめです。
文化祭で得られる貴重な情報
文化祭では、学校の雰囲気を感じるだけでなく、入学後に関わるかもしれない貴重な情報を得るチャンス です。
「説明会では聞けなかった!」と思うような話が、意外なところで見つかることもあります。
予約が大変な学校見学ツアー


文化祭では、「学校(校内)見学ツアー」 を開催している学校もあります。
在校生が参加者を案内し、30分程度の時間をかけて学校内を説明しながら歩くツアーです。
このツアーはとても人気があり、希望者が多すぎて参加できないことも あります。
私たちも、気になる学校のツアーに申し込みましたが、定員オーバーで参加できなかったことが数回ありました。



学校見学ツアーのメリットは多いです
- 効率よく校内を回れる
- 学校説明会では聞けない話が聞ける
- 在校生が「学校のいいところ」を紹介してくれる
特に、在校生の視点で語られる学校の良さは、パンフレットや説明会とは違ったリアルな雰囲気 を感じ取ることができます。
また、先生と生徒で「学校の特徴」として推しているポイントが違うこともあり、「在校生はこう思っているんだな」と知ることができるのも、このツアーならではです。
文化祭で見学ツアーがある学校では、できるだけ申し込んでおくのがおすすめです。
ただし、人気の学校では事前予約が必要 だったり、当日申し込みでもすぐ枠が埋まる ことがあるので、早めの行動が大事です。
中学入試相談コーナーが穴場


文化祭の入試相談コーナーは、意外と利用する人が少なく、じっくり話を聞けるチャンスの場です。



誰もいないので、入っていいのか躊躇するレベル
「入試相談」と聞くと、受験に関する細かい話をしなければならない場所 という印象を持つ人が多いですが、実際には 「学校の雰囲気」や「先生の考え方」などを直接聞ける場 でもあります。
でも、「入試のことを詳しく聞くつもりはないし…」と思ってしまうのか、文化祭に来た人の多くはこのコーナーをスルーしがち。
そのため、「先生と直接話せるのに、人が少なくて狙い目」 という、意外な穴場になっています。



時間制限なく話してくれる学校もありました
私は文化祭の入相談コーナーを利用して質問をたくさんしました。メリットはたくさん!
- 先生がどんなに些細なことでも親身に答えてくれる
- 入試の細かいポイントや出題傾向が分かる
- 文化祭だからこそ、時間をかけて話ができる
文化祭で入試相談コーナーを見つけたら、ぜひ利用してみてください。
質問したいことを事前にまとめておくと、より有意義な時間になりますよ。
私が中学入試相談コーナーで質問した項目などはこちら↓





実際の入試問題を持って帰れる学校もあります
文化祭に参加するときにチェック項目を決めておく


文化祭に行く前に、「どこを見ればいいのか」を考えました。
パンフレットや説明会では分からない部分も多いし、せっかく行くなら「この学校はうちの子に合いそう?」と感じられるかを知りたかったんです。
そこで、「私が実際に見ておいてよかった」と思ったポイント をまとめました。
学校の雰囲気
文化祭では、学校の雰囲気を直接感じることができるため、生徒の様子や先生との関係性、学校全体の活気 などを見ておくのが大事。
パンフレットには「アットホームな雰囲気」と書いてあっても、実際に行くと全然違うこともあるので、リアルな雰囲気をしっかり確認しました。
- 生徒の様子
- 先生と生徒の関係性
- 文化祭の盛り上がり
- 校舎や設備の状態



パンフレットの印象と、実際の雰囲気が違うこともあるよね。
通学のしやすさ
毎日通うことを考えると、通学のしやすさ はとても重要。
文化祭で学校を訪れたときに、最寄り駅からの距離や通学路の安全性 を確認しておくと、実際の通学イメージがしやすくなります。
特に、朝や夕方の人通りや、乗り換えのしやすさなどもチェックしておくと安心です。
- 最寄り駅からの距離
- 通学路の安全性
- 通学時間の許容範囲



通学ルート、実際に歩いてみると印象が変わることもありました
学食・売店の利用しやすさ
学食や売店は、学校生活のしやすさに関わるポイント。
学食の利用しやすさや売店の品揃え をチェックすることで、学校生活のイメージをつかむことができます。
特に、学食の価格やメニューの種類、売店で何が買えるのか を確認しておくと、入学後の生活が想像しやすくなります。
- 学食のメニューと値段
- 売店で買えるもの
- 自販機の種類



学食って言っても色々あるから、どんな形なのか見ておきたいね
部活動の雰囲気
部活動の活発さや雰囲気は、学校ごとの特色がよく出るポイント。
文化祭では、部活ごとの展示や発表を見ることで、活動内容や熱量 をチェックすることができます。
特に、子どもが興味のある部活が活発かどうか を確認しておくと、入学後の部活動選びの参考になります。
- 文化祭での部活の展示
- 発表内容 部員の活動の様子
- 学校全体の部活動の活気



文化祭の発表を見ると、部活の雰囲気がわかります
保護者の雰囲気(今後の関わり)
学校によって、保護者の関わり方には大きな違いがあります。
文化祭では、保護者がどのくらい学校に関与しているのか を知る良い機会になります。
バザーなどのイベントがある学校もあれば、ほとんど関与しない学校もあります。
また、部活動の応援が活発な学校もあれば、保護者が関与しない学校もあり、その違いを見ておくことも大切です。
- 文化祭での保護者の関わり方(バザー・イベントなど)
- 保護者同士のつながりの強さ
- 部活動の応援や関与の様子



学校によって、保護者の関わり方が全然違っていました
文化祭に行って実感!学校の雰囲気とリアルな様子
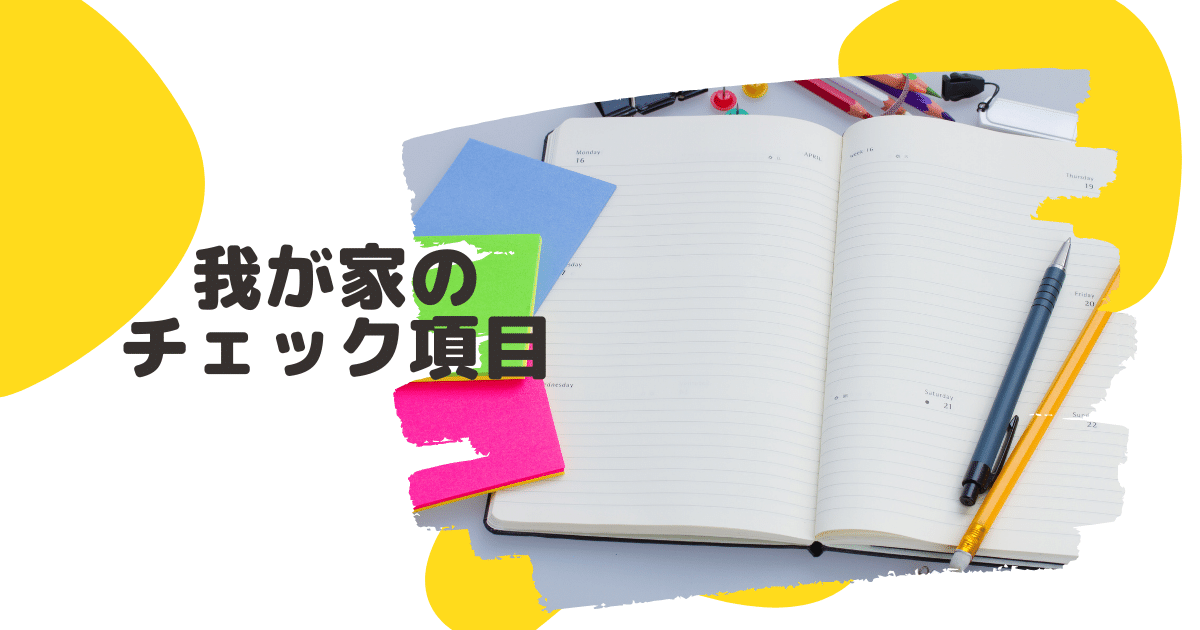

文化祭に行くと、パンフレットや説明会では分からなかった学校のリアルな雰囲気を感じることができます。
実際に学校に足を運んでみると、「こんな学校だったんだ!」と印象が変わることも多く、学校ごとの違いがはっきり見えてきました。
私が行った文化祭でも、生徒の雰囲気や先生との距離感、校舎の広さや設備など、パンフレットだけでは分からなかったことがいくつもありました。
学校説明会では「こういう学校です」と説明を受けても、実際に行ってみると、「あれ?思ってたのと違うな」と感じることもありました。
ここでは、私が実際に文化祭を見学して感じたことをまとめます。
通学のしやすさ
私自身、学生の頃に通学が大変だった経験があり、「子どもの通学はなるべく負担が少ないほうがいい」と考えていました。
だから、文化祭の見学では 「この学校、通いやすいのかな?」 という視点を意識してチェックしました。
- 通学時間は1時間以内
- 乗り換えは1回まで
- 最寄り駅からバスを使わずに歩ける距離
実際に学校に行ってみると、パンフレットの「徒歩○分」だけでは分からないことがたくさんありました。
地図で見ると近そうに見えても、実際に歩くと坂道が多かったり、信号が多くて思ったより時間がかかったりすることもあります。
また、地震や災害が起きたとき、迎えに行くのが現実的な距離かどうかも意識するようになりました。
「通学って、ただの距離じゃなくて、実際の負担も考えないといけないんだな」と実感しました。



実際に歩くと街の様子や気を付けたい場所などがみえてきました
学校の雰囲気
文化祭の見学で、私が一番重要視していたのは「学校全体の雰囲気」でした。
学校のカリキュラムがどんなに良くても、「この学校は合わない」と子どもが感じてしまったら、6年間通うのは難しくなります。
実際に見学を終えたあと、子どもに感想を聞くと、「この学校は絶対に通わない」と即答する学校もありました。
こういった場合は、無理に説得することなく、すんなり志望校から外すことができました。
逆に、「この学校は楽しそう、合っているかも」と感じた学校は、毎年文化祭に行っても印象が変わらず、最終的な志望校候補に残りました。



偏差値だけじゃなく、子どもに合う学校かどうかも大事ですね
先生の様子
文化祭では、先生の様子を見る機会が多く、どんなふうに生徒や来場者と接しているかが分かります。
ある学校では、先生がにこやかに挨拶をしてくれたのに対し、別の学校ではこちらから挨拶をしても無反応だったことがありました。
一つひとつの対応は些細なことかもしれませんが、「この対応おかしいな」と思ったら、その直感は大事にしたほうがいいと感じました。
パンフレットや説明会では分からない学校の雰囲気が、文化祭ではリアルに伝わってきます。
こうした空気感を肌で感じられるのが、文化祭見学の大きなメリットだと思いました。



なんか違和感あるな…って思ったら、それは大事にしたほうがいいかも
生徒の様子
文化祭は、生徒主体で運営されることが多く、先生があまり関与しない場面が増えます。
だからこそ、学校の普段の雰囲気がそのまま見える場面も多いです。
実際に見学してみると、こんな違いがありました。
- 来場者に「こんにちは!」と明るく挨拶してくれる生徒が多い学校もあれば、無言でスルーする学校
- 迷っていると、すぐに「どうしましたか?」と声をかけてくれる学校もあれば、特に気にせず通り過ぎる生徒が多い学校
- 友達同士で盛り上がっていて、来場者にはあまり関心がない学校
こうした生徒の姿を見ていると、「この学校はこの学校には、こんなタイプの子が多いんだな」 という自然と伝わってきました。
実際に子どもと話してみても、「この学校はちょっと合わないかも…」「ここなら楽しそう!」 という反応がハッキリ分かれることも多かったです。
学校のカラーは、偏差値やパンフレットの情報だけでは分かりません。
在籍している生徒の雰囲気を感じ取ることで、「うちの子がこの学校で6年間過ごせるか?」がイメージしやすくなりました。



在校生を見ると、なんとなく“この学校らしさ”が分かる気がします
展示物コーナーで感じたこと
文化祭の展示コーナーには、修学旅行や校外学習の発表がまとめられていることが多いです。
「この学校はどんな場所に行って、どんな学びをしているのかな?」というのが、展示を見ることで分かりました。
特に、校外学習のまとめ方には学校ごとの違いがあり、生徒が個人で自由にまとめている学校もあれば、学年全体で統一されたフォーマットで整理されている学校もありました。
「学校がどんなふうに生徒にレポートを書かせているのか?」も見えてくるポイントでした。



学校ごとに発表の仕方が違うから、見比べると面白かったです
学食と売店の利用しやすさ
すべての学校に学食があるわけではありませんでした。
学食がある学校では、メニューや売店の品揃えをチェックしました。
学食がある学校では、昼休みにどれくらい混雑するのか、メニューの種類がどの程度あるのかも気になるポイント。
学校によっては、日替わり定食や丼ものが充実していたり、おやつが売っていたりと、特徴が違いました。
一方で、学食がない学校は売店の品揃えが重要に。パンやおにぎりが買える学校もあれば、文房具や学用品のみの学校もありました。
また、学校内の自販機に飲み物がどのくらい揃っているのかも、見ておくと安心です。



冬は温かい飲み物、夏は冷たい飲み物があると嬉しいよね
部活動の雰囲気
文化祭では、部活動ごとの特色がよく表れます。
部員たちがどんな活動をしているのか、どんな雰囲気なのか、直接感じ取ることができるチャンスです。
我が家では、子どもが理科実験が好きだったので、毎回理科部の展示をチェックしていました。
理科部に興味を持つようになったのは、子どもが理科実験教室に通い始めたのがきっかけでした。
実験をするのが楽しくなって、「もっとやってみたい!」という気持ちが強くなったようです。


でも、学校によって展示内容も、生徒の対応も、かなり違いがありました。
- 解剖をしている学校
- 実験を体験できる学校
- 目の前で実験を見せてくれる学校
- 展示のみの学校
解剖をしている学校
アジやイカの解剖をしている学校はいくつかありましたが、亀の解剖をしていた学校は特に印象的 でした。
使用されていたのは駆除された個体で、大人の手ほどの大きさの亀。
白衣を着た生徒たちが、解剖の手順を説明しながら進めていき、実験室のような本格的な雰囲気 でした。
実際に見ていると、生徒たちの動きに無駄がなく、手際の良さが際立っていたのも印象的でした。
そして、解剖の途中で亀の体内から卵が出てくると、見学者の間から「おぉ!」と驚きの声が上がる場面も。
こうした実験の迫力や、実際に学んでいる生徒の姿勢が見られたのは、文化祭ならではの貴重な体験でした。
実験を体験できる学校
スライム作りや葉脈標本づくりなど、来場者が実際に実験できる学校 も多かったです。
ただ、こういった実験はどの学校でも似たような内容が多く、「去年別の学校でやったからいいや」 となることも多々ありました。
数校行けばどこかの文化祭で1回は体験できます。
手軽に参加できることからか、どの学校も行列ができていました。
目の前で実験を見せてくれる学校
炎色反応や液体窒素を使った実験など、科学ショーのように実演するタイプ の学校もありました。
実際に塾や理科の授業で習ったことが、目の前で起こると理解が深まる ようで、子どもも興味津々で見ていました。
展示のみの学校
実験は行わず、標本や研究レポートなどを展示する学校 もありました。
生徒さんが説明してくれる場合もあり、質問すると丁寧に答えてくれました。
ただし、小学生には少し難しい話が多く、大人は興味を持って聞けても、子どもは途中で飽きてしまうことも。
それでも、生徒さんが一生懸命説明してくれる姿勢は、学校の雰囲気を知る手がかり になりました。



興味のある部活は、いろんな学校で見比べると違いがよく分かるね
中学校の文化祭を見学した後には何をする?
文化祭は、見学して終わりではなく、見たことを整理して次のステップにつなげることが大切 です。
我が家では、文化祭のあと 「学校の印象を家族で話し合う」「メモを残す」 という2つを実践していました。
あとから志望校を決めるときに、この記録がすごく役立ちました!
学校の印象を話し合う
文化祭を見学したあと、子ども、主人、私の3人で学校の印象を話し合いました。
「話し合う」というと大げさですが、帰り道やご飯を食べながら、「どうだった?」と気軽に話すだけ。
それぞれ見る視点が違うので、意外な気づきがあって面白かったです。例えば



学校の門から教室まで距離がある、走っても遅刻するね。大丈夫?



あの学校の自販機にアイスがあったよ。学食は種類が少ないなぁ。



購買にパンとかおにぎりとか売ってる、お弁当を作れない日があっても安心。



プールがなかったよ、水泳の授業は無いね、やったー!



なんか雰囲気が合わなかった…この学校はやめとく
実際に文化祭を見学すると、「合う・合わない」がすごくはっきりする学校もありました。
パンフレットや説明会だけでは分からないリアルな雰囲気を、楽しみながら体感できるのが文化祭のいいところ ですね!
メモを残す
文化祭での印象は、時間が経つと忘れてしまうものです。
「どの学校がよかった?」「どこが気になった?」をあとから比較できるよう、メモを残しておくのがおすすめです。
手帳でもスマホのメモでもなんでもよくて、残しておくことが大事。
家族で話したことや、学校の特徴を簡単に記録しておくだけで、志望校を決めるときにすごく役立ちます。
例えば
- 学校の印象:「校舎が新しくてきれい」「生徒がみんな挨拶してくれた」
- 気になった点:「文化祭の雰囲気が落ち着きすぎていた」「学食が狭くて混雑していた」
- 子どもの感想:「ここは好き!」「ここはちょっと合わなそう」
また、中学受験専用の手帳などもありますよ。
詳しくはこちら↓



文化祭の感想は、時間が経つと忘れちゃうから、見学後すぐにメモするのがおすすめ
まとめ:中学の文化祭見学は、低学年から行くのがおすすめ
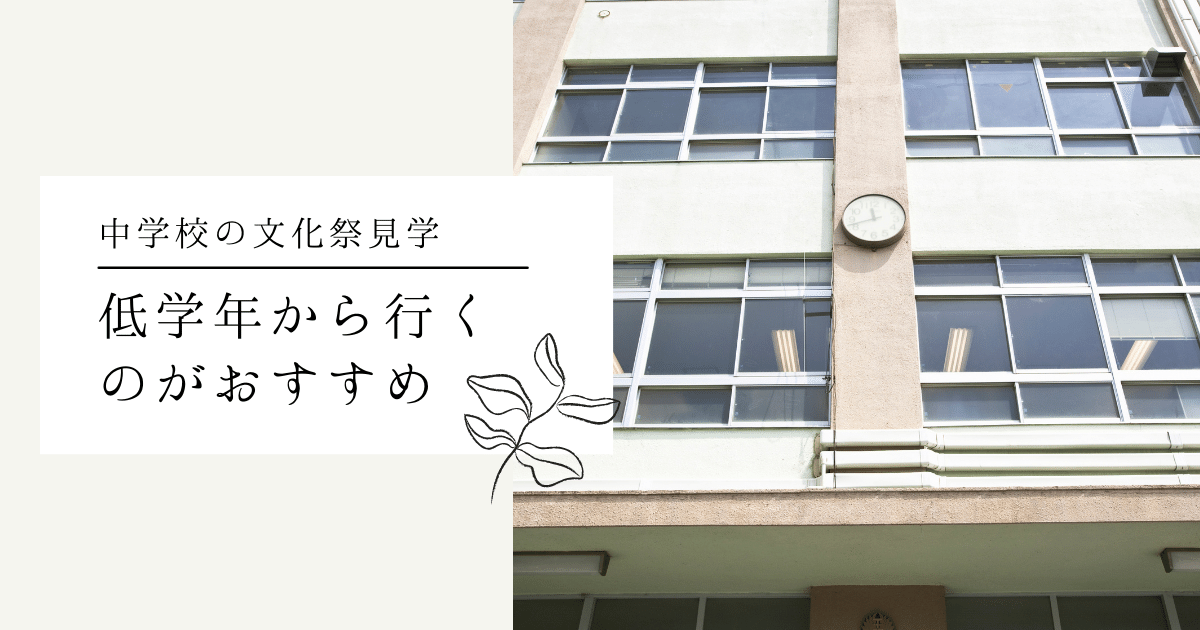

我が家では、小学校3年生から6年生まで、すべての文化祭を子どもと夫婦3人で見学しました。
子どもが気になった学校は何度も足を運び、年を重ねるごとに見る視点も変わっていった ことが印象的でした。
| 学年 | 文化祭見学の目的・ポイント |
|---|---|
| 3~4年生 | まずは「学校の雰囲気」を感じる。 1日1~2校ペースでゆっくり見学。 気に入った学校は翌年も再訪。 ※「この学校、合うかも?」という直感を大事にしてた |
| 5年生 | 「実際に通いたいか?」を意識。 気になる学校を再訪し、志望校リストを作る。 ※偏差値よりも「6年間通えるか?」を考える |
| 6年生 | 志望校がほぼ決まり、最終確認として訪問。 入試相談コーナーでの相談も活用。 ※塾や模試と重なり、文化祭に参加できる機会が少なくなる |
文化祭を見学することで、学校の雰囲気や通いやすさを実際に体感できる のが大きなメリット。
偏差値やパンフレットの情報だけでは分からない「この学校で6年間過ごせるか?」 を考えるきっかけになりました。
家族で見学すると、それぞれ違う視点で学校を見られるので、「思っていたのと違う」「意外と合いそう!」 など、客観的な意見を持てるのも良かったです。
塾で一緒だったお母さんの話では、文化祭の見学中に在校生から「うちの学校においでよ!」と言われたことで、子どもがその気になり志望校になった という話もありました。
実際に通っている生徒の姿を見て、「ここなら学校生活が楽しめそう!」と思えることもある ので、文化祭は志望校選びの貴重な機会となります。
6年生になると塾の予定で忙しくなるため、低学年のうちから少しずつ見学しておくのがおすすめ!
中学受験では、子ども自身が学校を選ぶことができます。だからこそ、文化祭を活用して、リアルな学校の雰囲気を知ることが大切です。
ぜひ文化祭を活用して、お子さんに合った学校を見つけてくださいね。
我が家のオープンキャンパス体験談はこちら↓










コメント